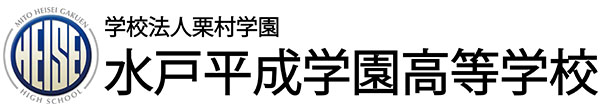保護者の皆様,在校生へ
学校から在校生の皆さまへのお知らせを掲載します。
-
2025年12月25日(木) [NEW]
就職への準備
「校長のつぶやき」12月25日(木)
昨日の午後、ハローワークから担当者を招いて「就職意識形成ガイダンス」を実施しました。この企画は、2年生の就職希望者を対象に、就職への準備をどのようにしておくのがいいかを学ぶために実施しました。当日、ハローワークから2名の職員が来校し、資料をもとに、参加した生徒たちへていねいに説明いただきました。私が気になったのは、資料の中に「新卒者3年以内離職率 中卒5割、 高卒4割 大卒等3割」という記載です。このことについては、いろいろな要因があるとは思います。安易に職場を変えることなく、与えられた場所で精一杯努力する若者を育てていきたいです。
校長 皆藤正造
※冬休み中ですが、昨日と今日、「校長のつぶやき」をお伝えすることができました。学校は12月27日(土)から1月4日(日)まで年末年始の休業となります。
-
2025年12月24日(水) [NEW]
社会化教育
「校長のつぶやき」12月24日(水)
本校では教育理念でもある「生きる力を育む」一環として、積極的にアルバイトを勧めています。社会で共有される行動規範や価値観を、生徒自らの体験を通して身につける「社会化教育」に繋がるからです。今回は、ある大学を合格した生徒の例を紹介します。たまたま自宅近くにある飲食店でアルバイトをすることになった生徒は、店長さんの計らいによりしっかりと責任を果たすことができるようになり、学校生活においても前向きになり、念願の大学合格を勝ち取りました。担任の先生は、「アルバイトでの経験が彼を前向きにした最大の要因です。」と話してくれました。人との出会いが人生の転機になった好事例です。
校長 皆藤 正造
-
2025年12月18日(木) [NEW]
学校全体が保健室
「校長のつぶやき」12月18日(木)
昨日から生徒対象の資格取得講座が始まりました。講座名は「赤十字 救急員養成講座」で、赤十字から派遣された講師が3日間の講習を担当し、突然の事故や急病になった時の一次救命処置及び応急手当の他、災害に役立つ知識を学びます。3日間の講習を受け、学科・実技の検定合格者には、日本赤十字社より救急法救急員認定証が交付されます。本校では、毎年この時期にこの講座を開設しています。
昨日は、講師として来校いただいた方が、過去に本校で養護教諭として勤務していた方で、応対した私と教頭で本校に関する話題になりました。その方が「ここは学校全体が保健室だよね。」とおっしゃってくださいました。学校の保健室は、体調不良はもちろん、気持ちが落ち込んだ時にも受け止めてくれる場所でもあります。当時から、悩みを受け止める体制が構築されていたことがわかる言葉を聞くことができ、とてもうれしい気持ちになりました。
※学校が冬休みになりますので、校長のつぶやきはしばらくお休みします。生徒や保護者の皆様、このコラムを見てくださっている方々が、良い年を迎えられることを祈念しております。
(校長 皆藤正造)
-
2025年12月17日(水) [NEW]
ありがとう
「校長のつぶやき」12月17日(水)
昨日は年末恒例の大掃除がありました。大掃除の前に生徒たちへ話をする時間があったので、当日参加した46名に、大掃除に参加してくれたこと(特別活動2時間履修扱いにはなります)へ感謝の意を伝え、また、生徒たちと一緒に1年間の振り返りをしました。
令和7年がもうすぐ終わるにあたり、無事に1年を過ごせたことに対して、誰に感謝するかを生徒たちに考えてもらいました。私は、学校生活に関しては支えてくれた先生たち、また学校でしっかり学んだ生徒たちに感謝することを伝えました。また、感謝の気持ちをもった人には直接「ありがとう」と言葉にしてほしいことも加えました。私は「ありがとう」をしっかり言葉にできる人間を育てたいです。
(校長 皆藤正造)
-
2025年12月16日(火) [NEW]
スクーリング最終日
「校長のつぶやき」12月16日(火)
昨日は今年のスクーリング最終日で、12月のレポート締切日でもありました。いよいよ令和7年度の学習のまとめの時期となります。年明けの最初の週は試験対策日課となり、その次の週から後期試験が始まります。レポートの提出やスクーリングの出席状況を見て、心配な生徒へ個別に電話をしている先生たちがいました。特に3年生は卒業を控えた大切な時期です。やるべきことをしっかりやって、新しい年を迎えてほしいです。
(校長 皆藤正造)
-
2025年12月15日(月) [NEW]
さすまた
「校長のつぶやき」12月15日(月)
先週、山形県の高校にナイフを持った女が侵入し、警察に逮捕されるという報道がありました。12日(金)の職員朝会で、この話題と本校の危機管理対応をあらためて確認しました。生徒以外の来校者は、事務室で用事を確認して対応します。本校の職員室は、廊下側に壁にないオープンな構造になっているので、来校者が校舎内に入ろうとすればすぐに確認できます。緊急事態が発生したら、連携をとって速やかに対応すること、生徒の安全を最優先することを確認しました。不審者対応の用具「さすまた」は事務室に設置してありシールに「沙悟浄くん」とあり、調べてみると商品名でした。
(校長 皆藤 正造)
-
2025年12月12日(金) [NEW]
心の中にいる
「校長のつぶやき」12月12日(金)
私が、小説や映画から亡くなった人(動物も)との向き合い方を学んだことを紹介します。人間と犬とのエピソードを題材にした数年前に発表された小説(映画化もされました)の中で、少年と兄弟のように育ってきた犬が、地震で少年をかばって命を落としました。犬の死を親が伝えると少年は胸に手を当てて「死んでないよ。ここにいるよ。」と言います。私はとても感動し、3年前に亡くなった我が家の愛犬も、私の心の中にいるような気がしてきました。また、先日近親者を亡くしましたが、同じように心の中で私を励ましてくれていると思っています。命が失われても、大切な記憶や思い出は無くならないでいつまでも存在するものだと考えるようになりました。
(校長 皆藤 正造)
-
2025年12月11日(木) [NEW]
上手な聞き方
「校長のつぶやき」12月11日(木)
昨日の午後4時間目に、茨城キリスト教大学大学院で心理学を学んでいる学生による心理学講座「コミュニケーションのコツを知ろう ~ 上手な聞き方 ~」を実施しました。本年度、本校で心理実習生として学んでいる3人の大学院生が指導者となり、エンカウンターグループの手法で2~3名のグループごとに、拒絶的な態度と受容的な態度でのロールプレイングを行い、その後振り返りを行いました。
最後に、相手が話しやすい聞き方の方法として傾聴技法の1つ「FELORモデル」を確認して終了しました 「F 顔を向ける E 適度なアイコンタクト L 耳を傾ける O オープンな態度 R リラックスすること。(英語のスペルは省略します)」私も家族から「話を聞いていない。」と言われることが多いので、参考にします。
校長 皆藤正造
-
2025年12月10日(水) [NEW]
人を励ます
「校長のつぶやき」12月10日(水)
先日、あるコンビニで機械でいれるコーヒーを飲もうとした際、同じようにコーヒーカップを機械にセットして待っている男性と何気ない会話になりました。お互いコーヒーが出来上がったタイミングで、別れ際に彼から「いい一日を!」と声をかけられました。何のかかわりのない初対面の方から今回のような言葉をかけてもらい、一瞬驚き、また、有難い気持ちになりました。今振り返れば、かけてもらった言葉へのお返しができなかった自分が情けなく、後悔しています。これからは、見ず知らずの他人にも励ましの言葉をさりげなくかけられるような人になりたいです。
校長 皆藤 正造
-
2025年12月9日(火) [NEW]
赤と白の葉ボタン
「校長のつぶやき」12月9日(火)
先日、最近まで校舎前で花を咲かせてくれていたニチニチソウから葉ボタンに衣替えをしました。本校職員のお知り合いで那珂市にお住まいの方が、地域の美化運動に協力するために花の苗を栽培しており、ニチニチソウの苗もこの方からいただきました。今回もご自分で種をまいて育てた見事な葉ボタンを本校の環境美化のためにわざわざ届けていただき、先日校舎前のプランターに植え込みました。冬の玄関に紅白の彩が加わり見事です。来春まで大切に育てていきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年12月8日(月) [NEW]
大学入試の課題論文
「校長のつぶやき」12月8日(月)
先日の職員朝会にて、進路指導担当者から次のような報告がありました。「大学の総合型選抜を受ける生徒の課題論文のテーマの難易度が高く、何度も指導を入れて完成しました。」あらためて与えられたテーマを聞くと、以下のような課題だったそうです。
「近年における世界各国の内向き指向に対して、日本は経済面においてどのような方向を目指していくべきか、あなたの考えを述べなさい。」(1,200字程度)
なかなかハードルが高く、一般の社会人でも文章にまとめるのは難しい課題です。このケースについては複数の教員で対応し、何度も添削を経て完成にこぎつけたそうです。本番の試験では、提出した論文をもとに受験者間でディスカッションもあるそうです。大学入試は大変です。
校長 皆藤 正造
-
2025年12月1日(月) [NEW]
水戸芸術館見学
「校長のつぶやき」12月1日(月)
11月29日(金)の午後、水戸芸術館を見学しました。この企画は、前回の近代美術館見学に続いて2回目となります。私も前半の企画展見学までの様子を参観しました。当日は、水戸芸術館を設計した著名な建築家 磯崎 新 の企画展が開催されており、たくさんの模型等の展示を担当者からの説明を聞きながら見学しました。その後は、ワークショップに移り、シンボルタワー(実物は高さ100m)の模型作りに取り組みました。水戸芸術館は、水戸市制100周年を記念して平成2年に開館し、開館35周年だそうです。磯崎新の企画展は1月25日まで開催しているので、興味のある方はぜひご来館ください。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月28日(金)
レポート締切日
「校長のつぶやき」11月28日(金)
昨日は、今月のレポート締切日でした。そのため、今週はいつもより登校してくる生徒も多く、2階の多目的ルームでレポートの仕上げに取り組んでいる生徒も多かったです。職員室前のカウンターでは、レポートを提出する生徒と教員のやりとりをたくさん見ることが出来ました。教員からの声掛けは、一人ひとりの生徒の提出状況を確かめながら行ってくれています。直接手渡しでの提出だからこそできる対話が、生徒と教員との関係づくりに欠かせない場面だと確信しています。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月27日(木)
安青錦のまなざし
「校長のつぶやき」11月27日(木)
大相撲、九州場所で初優勝した、ウクライナ出身の安青錦に関する話題をたくさん耳にしています。あるラジオ番組で、スポーツ記者が安治川部屋への入門時のエピソードを語っていました。相撲部屋は、部屋に外国籍の力士は1人しか所属させることができないので、経験の少ない彼を入門させるかどうか迷ったらしいですが、決め手は彼の目だったそうです。意志の強そうなキリっとしたまなざしが、親方の判断の根拠となったようです。安青錦のまなざしのような若者を育てるにはどうしたらいいか考えています。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月26日(水)
水戸の紅葉
「校長のつぶやき」11月26日(水)
昨日は体育の授業日で、午前中は水戸グリーンボウルでのボウリングでした。引率の先生や生徒たちと一緒にボウリング場で手配してくれたマイクロバスに乗せてもらい水戸駅から会場へ向かう途中、千波湖に近づくと赤や黄色く色づいた木々がたくさん目に入り、千波湖とのコントラストもきれいでした。その後、県立歴史館のイチョウが見事に黄色く色づいていました。当日の午後は、千波湖周辺のランニングの予定でしたので、生徒と一緒に走れることを楽しみにしていましたが、雨模様のため学校での講義に変更になり、現地に行けず残念でした。水戸市内にも紅葉がきれいな場所はたくさんあります。お時間がある方はぜひゆっくり散策するのをお勧めします。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月25日(火)
価格表示
「校長のつぶやき」11月25日(火)
先週の租税教室でお越しいただいた税理士の方と懇談していて教えていただいたことを記します。ものを購入する際の価格表示について、あまり気にしたことはなかったのですが、法律上は消費税込みの表示が義務付けられているそうです。しかし、実際には本体価格と消費税が分けて表示してある(税込み価格も併記されている)ケースが多いです。その理由は別々の表示が割安感を感じやすいからだそうです。世の中のことが分かったつもりでいても、知らないことがたくさんあることを実感する日々です。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月21日(金)
ビンゴの最大値
「校長のつぶやき」11月21日(金)
先日の平成祭で私が新たに学んだことをお伝えします。この間、通勤時に聞いていたラジオで、20代でビンゴをしらない割合が約70%という話題を耳にしました。確かに、宴会や大勢集まる機会のゲームとしてはポピュラーですが、コロナ禍の影響もありビンゴを体験したことのない若者は少なくないと思います。たまたま先日の平成祭ステージ企画で「ビンゴ大会」があり、私も1枚購入して参加しました。スクリーンに出た数字をめくりながら、ふと気が付いたのは1からの数字で最大値はいくつかということです。二桁の数字がたくさんあるので、「99までかな。」とつぶやいたところ、隣にいた生徒が「75までですよ。」と教えてくれました。あらためて調べてみると、いい具合に数字が並ぶ(確率を考慮して)ように75までにしてあるそうです。勉強になりました。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月20日(木)
租税講座とSDGs教育
「校長のつぶやき」11月20日(木)
昨日は、午前と午後に分かれて特別活動として2つの講座を行いました。午前中は、水戸税務署を通して、税理士の方が来校し、「税金」についての学びを具体例を交えながらお話くださいました。源泉徴収票を資料とした場面もあり、納税のしくみや税の活用について専門家から直接学ぶ貴重な時間となりました。午後は、NPO法人フリー・ザ・チルドレンジャパンから講師を招き、SDGs教育の一環として実施しました。前半は、グループに分かれて参加者同士が対話の大切さを学び、後半は社会の課題を解決するために自分ができることを考えるプログラムでした。今日の授業に参加した生徒たちが、自分を変えるきっかけにしてほしいと願います。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月19日(水)
笑顔いっぱいの平成祭
「校長のつぶやき」11月19日(水)
水戸平成学園高等学校の文化祭「平成祭」を11月15日(土)に実施しました。様々なステージ発表をはじめ、生徒たちが企画したイベントが校舎内外で繰り広げられ、保護者や一般の方々もたくさん来場していただき、楽しく充実した一日となりました。自分たちで考えたことをやり遂げる喜びは、生徒たちの表情が物語っていました。また、当日は多くの卒業生が来校してくれたことも印象に残ります。私も若者の笑顔と活力に接し、幸せな気分になりました。これからも教職員と生徒とともに、笑顔があふれる学校を作っていきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月14日(金)
3年生への面接練習
「校長のつぶやき」11月14日(金)
3年生は、大学進学・専門学校・就職に際して面接が課されることが多く、3学年職員や進路指導担当の出沼先生が担当となって、個別の面接練習を行っています。私も力になれればと思い、できる範囲でお手伝いをすることにしました。すでに数名の生徒の面接練習を担当しました。先生たちの指導を何度も経た状態での面接練習なので、本番を控えた本人に自信を持たせるように心がけています。この間担当した生徒に、本校のよいところを聞いたところ「困っていると先生たちが声をかけてくれる。」とこたえてくれました。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月12日(水)
平成祭への招待
「校長のつぶやき」11月12日(水)
11月15日(土)に、本校の文化祭「平成祭」が行われます。8月から2学年の実行委員を中心に準備をすすめ、いよいよ今週末に本番を迎えます。主な内容は以下のとおりです。
・ステージ発表(ファッションショー、軽音楽演奏、ダンスサークル発表)
・海王伝説(乗り物に乗って物語を味わってもらう)
・サークル発表(缶バッジづくり、射的、ヨーヨー釣り、わたあめ、カジノ、トランプ)
・占いの舘(お守り、おみくじ)
・飲食ブース(フランク、やきとり、アイスワッフル、揚げパン)+キッチンカー
・スタンプラリー
当日は、午前10時から午後3時まで一般公開いたしますので、このコラムをご覧のかたは、ぜひご来校くださいますようご案内申し上げます。校長 皆藤 正造
-
2025年11月11日(火)
いじめ防止対策推進法
「校長のつぶやき」11月11日(火)
今まで数回にかけて、学校教育における生徒指導に関することをお伝えしてきました。タイトルの「いじめ防止対策推進法」は、滋賀県大津市の中学校でいじめによる生徒の自死事件が発生したことをきっかけとして、国会において議員立法で平成25年に成立し、現在に至っています。法律の付則には、3年後に改正することになっていますが、未だに改正されていません。この法律は議員立法なので、議員の発議がないと改正できないのだそうです。法律ができて12年経ち、やっと周知が進んできました。しかし、法律を基に対応する学校や教育委員会にとって負荷がかかり、この法律を改正すべきであると意見を表明している教育学者等も少なくありません。私は県教委勤務から離れたので、今回このコラムを通して法律を改正すべきであるとの意見を表明いたします。学校や教育委員会は、いじめ問題について精一杯対応していることを申し添えます。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月10日(月)
出前授業「心理学への招待」
「校長のつぶやき」11月10日(月)
11月7日(金)の1時間目はホームルームです。今回は、福島県にある医療創生大学から講師を迎えての出前授業を行いました。講師は心理学部の鎌田真理子教授で、テーマを「フランクルから学ぶ『生きる意味』と『人生の意味』 ~心理学への招待~」として授業を行っていただきました。事前に内容を周知しておいたので、心理学に興味を持った生徒たちも参加したようです。授業では、ナチスからの迫害を受けた精神科医「ビクトール・フランクル」の足跡をたどりながら、「生きる意味」や「人生の意味」について考える時間となりました。当日いただいた資料から私が気に入った一節を紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フランクルは、幸福は求めることはできないもの。求めるほど、追えば追うほどにげていくものが幸福だと逆説性を説く。幸福を追うことをやめ、仕事にただ夢中になって没頭したり、愛する人を心をこめて愛し続けていれば、結果として、おのずと幸福は手に入ってくるものだと言います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
校長 皆藤 正造
-
2025年11月7日(金)
暴力行為
「校長のつぶやき」11月7日(金)
今回は暴力行為についてお伝えします。今回の調査で、茨城県の国公私立小中高校で発生した暴力行為は6493件となり、過去最多だったようです。学校別では、小学校は28.5%増の4667件、中学校は30.7%増の1588件、高校は37.6%増の238件でした。文部科学省は増加の背景として、いじめの認知に伴うものや児童生徒に対する見取りの精緻化によって把握が増えたことが考えられるとのこと。県教委は、同じ児童生徒が繰り返す場合もあるという分析をしています。暴力行為については、児童生徒が相手に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為をした場合と定義されているので、例えば、小学校低学年の児童がカッとして相手を蹴った場合もあてはまります。発生件数の増加は心配なことではありますが、それぞれの学校がきめ細やかな対応をし、トラブルの未然防止につなげてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月6日(木)
いじめ見逃しゼロへ
「校長のつぶやき」11月6日(木)
今回はいじめの件数についてお伝えします。「いじめ防止対策推進法」が施行され、いじめの件数が「発生」から「認知」に変わりました。これは、被害者の心情に配慮しての対応を推進するために「どこでも起こりえるもの」として取り扱うことになります。文部科学省も、認知件数の多い学校を「積極的に認知し、解消に向けて取り組みを始めている」と肯定的に捉えて、逆に少ない場合は放置されたいじめがある恐れがあるとしています。従って、以前の教育界では「いじめゼロを目指す」という言葉をよく耳にしあしたが、今は「いじめ見逃しゼロ」が大切になります。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月5日(水)
社会的自立
「校長のつぶやき」11月5日(水)
今回は、学校の不登校対応についてお伝えします。今回の調査では、小中学校の不登校児童生徒が全国で約35万人となり、過去最多となったようです。以前は不登校児童生徒への支援目標を「学校復帰」としていましたが、「教育機会確保法」の施行に伴い、無理に学校へ登校させることではなく、本人の将来を見据えて「社会的自立」を目標とするようにあらためられました。不登校はどの子にも起こりうる可能性があり、問題行動ではありません。いまだに学校以外での学びの場所が少ないなど、課題はたくさんありますが、社会全体で不登校児童生徒を支援する体制や意識づくりが進んでほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年11月4日(火)
近代美術館見学
「校長のつぶやき」11月4日(火)
10月31日(金)の午後、茨城県近代美術館を見学しました。この企画は、毎週金曜日の午後の2時間を美術の授業を実施しており、1年間に3回、美術の授業として近隣の施設を利用しての見学やワークショップを行っています。当日は教科担当の岩佐先生と茂垣教頭先生が引率しての実施でした。私も前半の様子を参観しましたが、学芸員さんからのオリエンテーションに始まり、企画展の鑑賞、缶バッジ作りのワークショップなど、貴重な体験となりました。近代美術館には4,000点の美術作品が所蔵されており、時期を見ながらその一部を公開しているそうです。優れた芸術作品を目の当たりにすると、心なしか心が豊かになったような気がしました。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月31日(金)
これっていじめ?
「校長のつぶやき」10月31日(金)
昨日の新聞等に、「小中不登校全国35万人」などの見出しで記事になっていました。これは文部科学省が毎年前年度のいじめや不登校などの全国調査をする「問題行動・不登校等調査」の結果が公表されたことによるものです。私は昨年度まで県教委の生徒指導・いじめ対策推進室で勤務しておりましたので、この機会にこのコラムをご覧の皆様に学校教育の生徒指導に関してご理解いただく機会とさせていただきます。例えば、ある学校で掃除をさぼっていたAさんを見かけたBさんが掃除をするように注意したとします。その言葉でAさんの心が傷ついたとして教師に訴えると、いじめ防止対策推進法では「いじめ」として認知します。その後、Aさんがこのことをきっかけに不登校になり欠席日数が30日を超えると「いじめ重大事態」(被害者はAさん、加害者はBさん)として学校は市町村教委へ報告し、調査をすることになります。いじめ防止対策推進法では、いきさつはともかく「児童生徒が心身の苦痛を感じたもの」としているからです。社会通念上のいじめとは違います。文部科学省もいじめの認知件数が多いというのは、学校が丁寧に対応しているとして肯定的にとらえています。他にもたくさんお伝えしたいことがありますので、次回以降もこの内容を続けます。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月30日(木)
万本桜プロジェクトへの参加
「校長のつぶやき」10月30日(木)
昨日は、本校が長い間関らせていただいている「いわき万本桜プロジェクト」への本年度2回目の参加日でした。約2時間バスで移動し、10時に現地に到着、その後、志賀代表の指示で4つのグループ(ゆず胡椒づくり、柿の収穫と渋抜き作業、伐採した枝の処理、昼食づくり)に分かれて昼食(昼食づくり班がつくった、羽釜炊きのご飯とカレー)を挟んで午後2時30分までそれぞれの作業に取り組みました。志賀代表をはじめとした、志の高い方々が取り組んできたプロジェクトの現場を目の当たりにすることは、人生の大きな財産になります。本校の生徒たちには、学校に在籍している間に1度は参加してほしいと願っています。
校長 皆藤正造
-
2025年10月29日(水)
昼休みの福拾い
「校長のつぶやき」10月29日(水)
昼食後の約20分、小さなビニール袋を持って学校周辺の福拾い(ゴミを拾うことを大谷選手にならってそう呼ばせてもらっています)をしています。近くのコンビニまで行き、裏通りを通って梅香トンネルの入り口まで行ってから学校へ戻ってきます。拾うものがまったくないことはなく、ペットボトルや空き缶、お菓子の袋などが見つかります。
先日、大リーグで活躍している山本由伸投手が、完投勝利を挙げた後、ベンチのゴミを全て片付けたことが記事で紹介されていました。本校の生徒たちが、世の中でゴミを拾う人になってくれることを思いながら福拾いをこれからも続けていきます。
校長 皆藤正造
-
2025年10月28日(火)
いろいろな人がいた方がよい
「校長のつぶやき」10月28日(火)
ある教育関係の研修資料に、「学校を安全・安心にするために」という項目があり、その中の1つに「多様性に配慮し、均質化のみに走らない学校づくり」がありました。その説明には、異質な要素を受け入れ多様性を重視するためには「いろいろな人がいてもよい⇒いろいろな人がいた方がよい」という発想の転換が大切だそうです。共生社会で生きていく私たちがしっかり心に留めておくべき言葉だと思います。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月27日(月)
選挙出前講座
「校長のつぶやき」10月27日(月)
10月23日(木)の午後は、特別活動 「主権者教育 茨城県 選挙出前講座」がありました。茨城県選挙管理委員会と水戸市選挙管理委員会から3名の職員が来校し、講座を担当してくれました。選挙や投票についてのレクチャーや、選挙本番に使われる記載台と投票箱を使っての模擬投票も体験させてもらいました。生徒の感想にも「将来投票に行く」との決意を書いている生徒が多かったです。7月の参議院議員選挙の際にも述べましたが、選挙権を確かに行使できるような意識づけを大切にしていきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月23日(木)
FACE TO FACE
「校長のつぶやき」10月23日(木)
昨日、ある職員と何気ない会話の中で、私から「うちの学校は面倒見がいいという評判だけど、その理由を先生はどう思う?」と声をかけたところ「FACE TO FACEだと思います。」と返答が帰ってきました。単位修得の時間数に限らず、登校する意志のある生徒が多い状況です。登校して教師と対面する機会が多くなれば、自然に人間関係が築かれて効果的な支援につながっているようです。「生徒と教員のFACE TO FACE」は本校の基本方針の1つでもあり、「自由に選べる登校日」との相乗効果が面倒見の良さにつながっているようです。
校長 皆藤正造
-
2025年10月22日(水)
探究ゼミ遠足と体育集中講義
「校長のつぶやき」10月22日(水)
昨日は2つの企画が行われました。1つは、探究ゼミ遠足で、生徒が行き先を仲間たちと相談しながら決定した遠足です。大型バスで埼玉県のイオンレイクタウンmoriに移動し、VSPARKでの自由行動、その後、東武動物公園に移動し公園内を見学しました。もう1つは体育集中講義で、午前中はグリーンボールでのボーリング、午後は校舎2階での卓球とモルックを行いました。モルックはフィンランド発祥のスポーツで、木の棒を投げて得点を競う競技です。狭いスペースでできる、戦略的なスポーツです。それぞれの企画の担当者から、生徒が意欲的に活動できたとの報告がありました。
校長 皆藤正造
-
2025年10月21日(火)
成長の過程
「校長のつぶやき」10月21日(火)
10月17日(金)に、本校に勤務しているスクールソーシャルワーカーを講師に、校内研修を行いました。研修のテーマは「発達凸凹や愛着形成に課題がある生徒の理解と対応」です。講話の中では、発達障害という言葉の障害にあたる「おくれ、ゆがみ、かたより」は誰にでもあること、最近は「発達障害」という言葉に代わり「神経発達症」という言い方が使われる傾向にあることなどを学びました。講師から受けた「子どもたちは成長の過程であること」「いつも変わらず成長を促す温かな対応が大切なこと」を教職員で共有し実践していきます。
校長 皆藤正造
-
2025年10月20日(月)
県教委主催の通信制等高校説明会
「校長のつぶやき」10月20日(月)
10月19日(日)に、茨城県教育委員会が主催する「県内通信制及びフレックス制高等学校合同学校説明会」が、茨城県水戸生涯学習センター(旧県庁)で開催されました。県教委主催の合同説明会は今年度で3回目の開催となります。この企画は、県内の生徒が多様な学びの場を選択できる機会を提供するためです。当日の会場は3階の大講座室となり、直接会場に足を運ぶ集合型参加を定員100名とし、オンラインでの参加も300名までの参加となっていました。本校からは茂垣教頭先生が参加して説明をしてくれました。当日の各校の説明については、後日県教委のHPにアップされるそうです。会場には私の知り合いの中学校の職員も会場におり、通信制高校についての制度を理解するために参加したとのことです。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月17日(金)
地鎮祭
「校長のつぶやき」10月17日(金)
本校は、現在の駐車場の敷地(駐車場の西側のスペース)に、あらたに多目的ホールとして使用する校舎の増築を予定しています。昨日は、工事の安全祈願のための地鎮祭が執り行われました。学校からは栗原理事長、中村顧問と私が参列し、設計事務所や施工業者の方々と一緒にこれから行われる工事の安全を祈願しました。これから本格的な工事に入りますので、現在の駐車場のスペースに制約がかかります。保護者の皆様方にはご理解とご協力をいただけますようお願い申し上げます。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月16日(木)
IQ150
「校長のつぶやき」10月16日(木)
昨日は茨城県私学教職員研修会が、鹿島学園高校を会場に行われ私が参加しました。午後に、生成AIを学校教育に活用することを研究されている札幌国際大学、安井政樹氏の演題「生成AI時代の学びの在り方」の講演会がありました。文部科学省は、生成AIの活用を積極的に推奨していること、今は航空機や鉄道と同じく社会インフラとして生活に欠かせないツールになっていることなど、まさにタイムリーな内容でした。特に印象に残ったのは、今のAIはIQ150の実力があるので信頼度が格段に向上しており、優秀なアシスタントとしてぜひ活用して仕事の効率を高めてほしいとのことでした。※IQ100が普通の大人レベル IQ150になると全体の最上位2パーセントに位置し、非常に優秀なレベルだそうです。
校長 皆藤正造
-
2025年10月15日(水)
駅から2.1㎞
「校長のつぶやき」10月15日(水)
先日、スクールバスに乗り遅れた生徒が私に「水戸駅まで歩いてどのくらいかかりますか?。」と聞いてきたので、「だいたい30分くらいかな。」と答えました。それを聞いた本人は、「止めときます。」との返事でした。その後職員室に戻り、職員にどれくらいの距離があるのか聞いたところ約2.1㎞あることがわかりました。散歩の目安は1時間で4㎞だと言われます。水戸駅から学校まで約30分、自分の足で歩いてみるのもいいかと思います。在校生の皆さん、時間がある時にぜひチャレンジしましょう。
校長 皆藤正造
-
2025年10月14日(火)
「お仕事図鑑」
「校長のつぶやき」10月14日(火)
10月10日(金)の1時間目 3学年合同のホームルームがありました。内容は、一般社団法人ハッシャダイソーシャルから派遣された講師による企画で、5月23日に続いて2回目です。派遣元のハッシャダイソーシャルは、高校や児童養護施設、少年院等を対象に講演活動に取り組んでいる団体です。今回は「お仕事図鑑」というテーマで、講師の大本さんの進行で、実際に働いている方々(日新火災海上保険株式会社 水戸支店の職員2名)を招いてインタビュー中心の内容でした。実際に保険業に携わっている方から生の声を聞くことができ、参加した生徒たちも参考になったようです。
校長 皆藤正造
-
2025年10月10日(金)
ニュースを知らない
「校長のつぶやき」10月10日(金)
昨日の職員朝会で、3年担当職員のスピーチ(本校では日直当番の職員が司会進行し、最後に自分のスピーチをすることになっている)の中で、3年生の面接練習から感じた話題が出ました。就職や専門学校・大学進学等に面接が課されることが多いので、教員が指導者となって面接練習を行っています。その際、生徒が最も苦手とするのが「最近のニュースで関心のあることは何ですか。」だそうです。自分の好みのSNSなどは頻繁にアクセスするかわりに、世の中で起きている出来事には触れる機会が少ないようです。たとえば、7月に水戸で発生した無差別殺傷事件を知らない生徒もいるようです。世相に関心を持たせるためにはどうすればよいのかを思案しています。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月9日(木)
学びをつなぐ
「校長のつぶやき」10月9日(木)
今週の7日から9日の午後は、今年度の前半に本校に転入してきた生徒対象の前期試験を実施しています。高校からの転入ですので、単位修得のために課すものです。本校では毎年50人以上(昨年度は57名)の転入生を受け入れています。学びを継続したい高校生を支えるのも水戸平成学園高校の使命です。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月8日(水)
折れない心を育てる
「校長のつぶやき」10月8日(木)
10月6日、茨城県教育研修センターを会場に、文部科学省主催の「児童生徒の自殺予防に関する啓発研修会」が行われ、本校からは砂川先生が参加しました。当日の資料を見せてもらい、参考になったことを紹介します。 危機に陥っても折れない心を心理学では「レジリエンス」といい、この力を育てることが大切だと言われます。レジリエンスの構成要素の1つに、援助希求できる力(困った時に助けをもとめること)があります。「大人になる≒自立≒適切に依存できる力 」だそうです。困った時には一人で悩まず、助けを求めることが大切なんですね。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月7日(火)
理由を10個考える
「校長のつぶやき」10月7日(火)
ある教育雑誌に掲載られていた記事を紹介します。オランダでは、「教師は生徒を頭ごなし怒鳴るものではないという考えが一般的で、子どもが何か問題行動をしたらその背景にある理由を10個考えてみる。」のだそうです。また、ベルギーやオランダの教師は、自身の働き方にゆとりがある分、生徒にも穏やかに向き合い、「対話」によって問題解決する文化があるようです。それぞれのお国柄によって、教師の仕事ぶりも違うようですが、「理由を10個考える」はとても参考になるフレーズです。
校長 皆藤正造
-
2025年10月6日(月)
女性の活躍
「校長のつぶやき」10月6日(月)
自民党の総裁選挙の結果、高市早苗氏が自民党総裁となり、次の総理大臣に就任する見通しのようです。今朝、通勤時のラジオでこのことが与える影響について、コメンテーターが意見を述べていました。その中の1つに「女性の活躍が進むだろう」というものがありました。女性の活躍推進については、我が国の重要課題の1つです。私もある教育雑誌に、「女性の活躍を進めるには、学校の管理職に女性を積極的に登用すること、なぜなら、子供たちが上に立つ人が女性であることが自然だと思うようになるから。」という記事を目にし、心に留めておきました。私は、女性が活躍する社会を望んでいる一人です。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月3日(金)
定時制・通信制で輝いている生徒たちの発表
「校長のつぶやき」10月3日(金)
10月2日(木)、つくば市の市民ホールくきざきを会場に、令和7年度茨城県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会が開催されました。この行事は、県内の公立・私立の定時制や通信制高校で学ぶ生徒の代表が、自分の今までの生活を振り返り、高校生活の様子や将来の夢を語るものです。当日は22名の生徒が出場し、本校からも横山 聖菜さんが学校を代表して発表しました。どの生徒の発表も、自分の過去の経験を振り返りながら、未来に向かって力強く歩んでいる内容で、とてもすばらしかったです。私自身も、生きることの力強さや人生の幅が広がる機会となりました。また、通信制高校で学ぶ生徒を預かる者としての責任の重さを自覚する時間となりました。
校長 皆藤 正造
-
2025年10月2日(木)
つくば霞ヶ浦りんりんロードサイクリング
「校長のつぶやき」10月2日(木)
10月1日、後期の最初の授業は体育集中講義として毎年この時期に実施している「つくば霞ヶ浦リンリンロードサイクリング」でした。朝から雨模様だったので開催できるかどうか心配でしたが、土浦市にあるサイクリング施設「りんりんポート」に到着してみると小雨はふるものの、気にならない程度の天候でした。サポートしていただくサイクリング関係者と相談し、安全面を考慮してかすみがうら市方面へのコースに変更しました。私も生徒たちと一緒に自転車で走りましたが、暑さが気にならない分、快適なサイクリングでした。レンタルされたクロスバイク(ハンドルがまっすぐなスポーツタイプの自転車)に乗って霞ヶ浦湖畔のサイクリングロードを走ったことは、参加した生徒たちにとって貴重な体験になったようです。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月30日(火)
前期を終えて
「校長のつぶやき」9月30日(火)
今日で本年度の前期が終了、明日からは後期の学校生活が始まります。3年生にとってはすでに進路決定の大切な時期を迎えており、就職や専門学校、大学への入試等に備えた面接練習が頻繁に行われています。玄関には、就職や専門学校のへの内定を得た生徒の氏名が掲示されるようになりました。職員室で生徒と電話している教員の会話からは、単位修得のための個別なアドバイスをしている様子がわかります。様々な背景がある生徒たちに対して、丁寧に伴走支援している教職員の働きぶりには頭が下がります。本校の目指す学校像の1つ「一人を大切にする教育」を実践できていると確信しています。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月29日(月)
土曜日の学校説明会
「校長のつぶやき」9月29日(月)
保護者の方々や生徒の皆さんが予定を立てやすいように、毎月第2,第4の土曜日に学校説明会を実施しています。9月27日(土)は6組の訪問があり、学校概要の説明や校舎見学をしてもらいました。高校進学を控えた中学生と保護者、または、転校を検討している高校生と保護者など、様々なケースの相談を受けています。土曜日の学校説明会については、事前に電話をいただいての予約が必要です。もちろん、平日も実施しておりますので、電話等でご相談ください。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月26日(金)
騙されないための教科書
「校長のつぶやき」9月26日(金)
先日、青少年育成関係団体が作成した資料が学校に届きました。そのタイトルが「騙されないための教科書」です。近年増加する若者をターゲットとした詐欺や悪徳商法から被害に遭わないための注意点をまとめた冊子です。強調されていた3点は以下の通りです。
「うまい話には裏がある」「衝動的に行動しない」「1人で抱え込まない」
若者に限らず、新聞記事には連日のように、警察官を語るものからの詐欺被害、SNSでのロマンス詐欺、投資に関する詐欺などが報道されています。高校生はもちろんですが、詐欺にあわないために心して生活しなければならない世の中になってしまったことが残念です。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月25日(木)
追試験中です
「校長のつぶやき」9月25日(木)
前期試験の結果、基準(30点以上)を満たさなかった生徒や未受験の生徒については、追試験を課します。実施期間は9月24日(水)~30日(火)で、朝が苦手な生徒にも配慮して午後の時間帯に4つの試験時間を設定しています。該当する生徒は各自の予定で登校し、自分が受験する科目の試験を受けることになります。教科担当者は追試験受験者へ対策プリントを用意し、試験が合格ライン(30点以上)を超えるよう支援をしています。単位を修得するためのハードルをしっかり超えてくれることを願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月24日(水)
20年目の創立記念日
「校長のつぶやき」9月24日(水)
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、厳しい暑さもかなり和らいできました。9月22日は本校の創立記念日でした。平成17年に開校したので、今年度はちょうど開校20年となります。学校教育は学びの多様化の時代を迎え、通信制高校の存在意義も高まっています。本校の基本理念「すべての生徒に「生きる力」を育む」を目指し、今まで培った本校の伝統を大切にしながら、新たな時代に合った教育活動を展開していかねばと思います。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月19日(金)
見るスポーツの効能
「校長のつぶやき」9月19日(水)
9月13日から東京国立競技場で開催されている世界陸上も残りわずかとなりました。長い時間ライブでテレビ放映されているので、ご覧になった方も多いと思います。競技の様子や選手のインタビューなどで感動する場面がたくさんあり、「見るスポーツの効能」についてあらためて知りたくなり、調べてみました。すると、スポーツを観戦することは大変な癒しと励ましになるとともに、疲れた心を鼓舞してくれる効果がある。また、スポーツは勝ちか負けか、つまり「白・黒」をはっきりさせることが、観客の心地よさを引き出しているそうです。確かに、私のここ最近の大きな思い出は、3年の平岡陵照さんが出場した日本武道館で行われた剣道の全国大会の応援でした。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月18日(木)
オセロとスティーブ・ジョブス
「校長のつぶやき」9月18日(木)
今日は大掃除の日で、登校してくれた生徒たちと教員で1時間近く校舎内をくまなくきれいにしました。朝の集会で生徒たちに話をする機会があったので、学校生活前半が終える節目でもあり「過去をどうとらえるか」という内容の話をしました。まず、「人生はオセロだ」という言葉を示しました。途中が黒でも次に白がくれば黒はすべて白になる、黒は次に白が来る布石であり糧になるという考え方です。また、アップル社の創業者スティーブ・ジョブスがスタンフォード大学の卒業式で述べたいわゆる「伝説のスピーチ」の中で「点と点をつなげる」ことを話しています。過去の出来事が後になってつながり実を結ぶことの例えとして示しました。人生においては無駄な出来事は一切なく、必ず自分の糧になります。本校の生徒たちが、目の前のやるべきことに力を精一杯注く若者に育ってほしいです。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月17日(水)
草花の切り戻しと再生
「校長のつぶやき」9月17日(水)
校舎前のプランターで育てていた日日草(ニチニチソウ)が大きく育って花を咲かせてくれていましたが、枝が伸びてきたので切り戻しをしました。草丈の半分位のところでハサミをいれたので、一旦は花が無くなります。このあと、切られた枝から脇芽が出て育ち、再びたくさんの花をつけてくれるはずです。私自身も、教育に関する考え方や理想の学校像などを時代に合ったものにアップデートしなくてはと考える今日この頃です。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月16日(火)
敬老の日に思う
「校長のつぶやき」9月16日(月)
昨日は9月15日、敬老の日としての祝日でした。65歳以上が「高齢者」とされるので、私もその仲間に入ります。「敬老の日」のおかげで「うやまう」という日本語を学んだ記憶があります。ひと昔前は、お年寄りを敬う日という印象がありましたが、昨今はどうでしょう。報道でも、高齢者の就業率等が示されたり、「健康寿命」の大切さについて啓発する記事も多いと感じます。いつまでも元気で働ける、社会貢献できる機会がたくさんある、そんな社会になることを期待しています。
校長 皆藤正造
-
2025年9月12日(金)
文章力
「校長のつぶやき」9月12日(金)
今週は前期試験が行われています。昨日の職員朝会にて職員から「文章で答える問題への解答を見ると、漢字で書けない、文章の意味がとおらないなどのケースが多い。」との話がありました。また、中村顧問からも、小中学校の関係者から「今の子どもたちは、文字を書いたり、文章をまとめたりする力が心配である。」と指摘している声をよく聞くそうです。パソコンやスマートフォンの普及で、直接文字を書いたり文章をまとめる機会が少なくなったこともあるかと思いますが、大切な力であることは言うまでもありません。この現状を踏まえて今後の指導に生かすことを職員間で共有しました。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月11日(木)
知事選挙33.52%
「校長のつぶやき」9月11日(木)
9月7日に行われた茨城県知事選挙は、新聞報道等によると投票率は33.52%でワースト5位だったとのことです。投票率が低い要因は様々だと思いますが、参政権を行使しない人たちが多い現実が心配です。18歳となって選挙権を有している者、これから選挙権を得る者を預かる立場として、「選挙があれば必ず投票に行く」意識を醸成していければと思っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月10日(水)
通信制高校への関心
「校長のつぶやき」9月10日(水)
9月6日(土)に、水戸市民会館にて県内通信制高校の学校説明会が行われました。本校からは茂垣教頭と郡司先生が参加し、来場者への説明を担当しました。私も当日の午前中に足を運び、様子を参観しました。水戸市民会館3階の広いフロアが会場となっており、県内の主な通信制高校がそれぞれブースを設け、来場した保護者や生徒の相談に対応する形です。今回の学校説明会は、民間の教育団体が主催して事前の申込みを経て来場した方もいたようですが、各学校のブースで担当者の話を聞く様子が途切れませんでした。私にとって、通信制高校への関心の高さを肌で感じた一日になりました。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月5日(金)
前期試験がんばれ
「校長のつぶやき」9月5日(金)
朝から雨模様で、酷暑もいくぶんやわらいだ一日を迎えました。校舎前のプランターは、保健室の金澤先生が持参してくれた日日草(にちにちそう)の苗が大きく育ち赤・白・ピンクの花をつけ私たちを迎えてくれます。今週はテスト対策日課で、教科担当者が作成した試験対策プリントを用いて特別授業が連日行われ、多くの生徒が登校し試験に向けて学んでいました。次週は本番の前期試験が行われます。単位修得には欠かせない大切な試験なので、日ごろの学びをしっかり発揮してほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年9月4日(木)
高校生のボランティア活動
「校長のつぶやき」9月4日(木)
学校に9月27日(土)千波湖周辺コースで行われる「茨城シャインシャインマスカットラン」へのボランティア参加案内の資料が届きました。私は、この大会を主催する団体が既に実施している「水戸メロンメロンラン」には毎年参加しています。この大会は、千波湖の周回コースを使って給水所の代わりにメロンの食べ放題ブースを設置して、ランニングしながらメロンを味わうことのできる楽しい大会です。今年も6月8日に実施され、9kmの部に出場しました。大会当日は、千波湖周回コースに約50mおきに高校生と思われる補助員がおり、参加したランナーに「頑張ってください!」と声をかけてくれました。走りながら数名の補助員に「アルバイトですか?」と声をかけると、声をかけた全員が「ボランティアです!」と答えてくれました。私はこの暑い中、ボランティアではなくアルバイト等で参加しているものと思い込み、主催者からの指示でそう答えているものと思い込んでいました。ところが、今回の大会資料を見て、過日の大会の補助員もボランティアだったらしいことがわかり、疑った自分が情けなくなりました。今回の大会のボランティアへの支給品は スタッフTシャツ お弁当、ボランティア証明書、シャインマスカット1房だそうです。私も、シャインマスカットを使った初めての大会なので参加したかったですが、都合により不参加です。
校長 皆藤正造
-
2025年9月3日(水)
生徒が企画する遠足
「校長のつぶやき」9月3日(水)
植松先生が担当する「探究ゼミ」に参加した生徒たちが企画した遠足を実施します。7名の生徒が参加し、ゼミの時間の中で「10年後も思い出に残る遠足」をテーマに、日帰りで行ける範囲の見学地について調査するなど、準備を進めてきました、授業でのプランがまとまり、学校としてGOサインを出し、正式な募集までこぎつけました。
学校の魅力は「生徒が主役であるかどうか」が1つの尺度となります。今後も生徒への信頼を基盤とした学校をつくっていきます。校長 皆藤正造
-
2025年9月2日(火)
映画を一緒に見るような感じで
「校長のつぶやき」9月2日(火)
ある教育相談に関する研修会資料で見つけた、傾聴のイメージを言い換えた言葉です。教育相談を学ぶことは、教育関係者にとっては欠かせないスキルの1つです。私自身も、幾度も関連する研修会に参加し、クライアント(相談者)の声を傾聴することの重要性について理解はしたものの、なかなか他の人に伝えるときにわかりやすい表現がありませんでした。他にも「ストーリーを変えようとしないこと」だそうです。
校長 皆藤正造
-
2025年9月1日(月)
9月1日は何の日
「校長のつぶやき」9月1日(月)
今日から9月になりました。9月1日は防災の日ですが、ここ最近は子供の自殺が1年間で最も発生やすい日として認知されています。 在る資料によると、アメリカの10万人あたりの自殺者数は日本の約半分だそうです。その理由は、「子供は悩みを同年代の仲間に打ち明ける。打ち明けられたら、責任ある大人へつなげる。」ことを徹底しているそうです。アメリカの自殺予防教育で特に強調される点は、「問題を抱えることは誰にでもある。問題を1人で抱え込むな!」を原則として指導に当たることだそうです。今朝の職員朝会でこのことを話題にし、教職員に対して「生徒への声掛けと情報共有の大切さ」について確認しました。
学校も今日から試験対策日課(テストに向けた対策プリント中心の授業)が始まり、多くの生徒が登校し、来週の試験に向けての学習に取り組んでいます。
校長 皆藤 正造
-
2025年8月27日(水)
保護者会にて
「校長のつぶやき」8月27日(水)
8月23日(土)の午前中に、本校の保護者会を開催しました。メールにて開催を案内し、事前にいただいた質問等への学校からの回答、各学年の学校の状況等を説明しました。最期に、学年職員を交えて保護者同士の情報交換の時間を設けました。内容は、参加らされた方々が日ごろ感じている悩み(自宅での生活、アルバイト、友人関係、ゲーム依存など)を共有しながら教員を交えて意見交換をされました。コロナ禍前は定期的に希望する保護者の方々が集う機会を設けておりましたので、今後、再開する方向で検討していきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年8月22日(金)
志望理由書をまとめる
「校長のつぶやき」8月22日(金)
8月20日の午前中、大学や専門学校志望の生徒を対象に、志望理由書講座を行いました。この講座は進路指導部が中心となって、総合型選抜入試等で求められる志望理由書のまとめ方を指導するものです。進路指導担当の出沼先生があらかじめ用意した資料をもとにまとめ方のポイントを指導し、その後は各自希望する学校の入試要項に合わせて文章をまとめていきました。具体的には、ある大学では「高校での体験と志望理由を400字以内でまとめる」「大学4年間でどのように学ぶかを800字以内まとめる」など、どの学校もなかなかハードルが高い内容でした。個別の文章作成の場面では、出沼先生の他に数名の教師が入って個別にアドバイスしました。私も生徒たちが真剣に取り組んでいる様子を見ながら、あらためて文章をまとめる大変さを実感しました。今後は、希望する生徒とはメール等で連絡を取り合い、本番の出願に向けて準備していく予定です。
校長 皆藤 正造
-
2025年8月19日(火)
生徒が企画運営したオープンキャンパス
「校長のつぶやき」8月19日(火)
今日の午前中(10時~12時)、中学生対象のオープンキャンパスを開催しました。前半の活動は、在校生と参加した中学生が4人から5人でグループを構成し、グループワークやクイズ等で和やかな時間を過ごしました。後半は生徒たちが自ら作成編集した映像資料を使っての学校紹介、グループごとに校内の施設見学等を行いました。約2時間のプログラムを進行も含めてすべて生徒たちが担って実施することができ、あらためて高校生の行動力に感心しました。
校長 皆藤 正造
-
2025年8月18日(月)
LGBTQ+ 20人に1人
「校長のつぶやき」8月18日(月)
8月7日(木)ホテルレイクビュー水戸において、茨城県私学教職員研修会が開催されました。当日の研修の中で、講演「LGBTQ+を入り口に考える ―性の多様性と共生社会の実現―」があり、NPO法人プライドハウス東京・理事の鈴木 茂義氏の約90分の講演を拝聴しました。鈴木氏は茨城県出身で東京都の元公立小学校の教諭を経て、現在はNPO法人に所属して、今回のテーマ等の理解啓発のため全国での講演活動等に取り組んでいる方です。鈴木氏自身もLGBTQ+の当事者であり、自身の体験談をはじめ、私にとってたくさんの示唆をいただきました。当日の資料から LGBTQ+とは
L(レズビアン・女性同性愛者)× レズは蔑称
G(ゲイ・男性同性愛者) × ホモ・オカマは蔑称
B(バイセクシャル・両性愛者) × バイは蔑称
T(トランスジェンダー・性別違和)× オネエ・オナベ・ニューハーフは蔑称
Q(Queer クィア)変わった・風変りな・個性的な
(Questioning クエスチョニング)決めたくない・決められない・わからない
+ アセクシャル 他者に対して性的欲求を抱かない、もしくはほとんどない
アロマンティック 他者に対して恋愛感情を抱かない、もしくはほとんどない
上記のような性の多様性がある人の割合は約5パーセント(約20人に1人)とのことです。視野を広く持って教育活動に関わる大切さを自覚できた時間でした。
校長 皆藤 正造
-
2025年8月5日(火)
祝 剣道全国大会準優勝
「校長のつぶやき」8月5日(火)
8月4日(月)に令和7年度全国高等学校定時制通信体育大会第56回剣道大会が東京の日本武道館で開催されました。本校からは平岡陵照さんが男子個人戦に出場したので、私も応援のため会場に足を運びました。男子個人戦は、各都道府県の大会を勝ち抜いた79名が出場しました。平岡さんは昨年度も3位に入賞しており、今大会はトーナメントの第2シードからの試合でした。初戦から準決勝までの5試合は圧倒的な実力を示し、すべて2本勝ちで決勝まで勝ち上がりました。決勝の相手は昨年度の優勝経験者との戦いとなり、日本武道館のセンターコートで息詰まる熱戦を展開しました。試合時間4分、その後の延長4分でも決着がつかず、再延長4分の半ばに相手の飛び込み面に審判の旗3本が上がり、惜しくも準優勝となりました。2年連続全国大会で上位入賞した平岡さんの快挙に敬意を表します。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月31日(木)
震災体験を語り継ぐ
「校長のつぶやき」7月31日(木)
昨日は朝から携帯電話の緊急速報が幾度もあり、落ち着かない1日でした。ご家庭で、海岸近くにお住まいの方は大変な一日であったと推察いたします。昨日、ふと感じたのは、2011年に発生した東日本大震災のことです。当時は様々な苦難があり、それを乗り越えて現在があります。本校に学んでいる生徒たちは15歳以上ですから、1年生が震災当時に生まれたばかり、3年生の18歳でも3歳から4歳なので、明確な記憶はないでしょう。保護者の方々の中には、幼子を抱えて大変な思いをされた方もいらっしゃると思います。
今日の職員朝会で職員に対して、震災経験者としてこれからの社会を支えていく若者へ自分の体験を語り継ぐことの大切さを確認しました。
校長 皆藤正造
-
2025年7月28日(月)
進路指導とは
「校長のつぶやき」7月28日(月)
先日中村顧問の知人が来校されました。その方は県内の公立私立高校の校長を長らく務めた方で、私も同席していろいろとお話を伺うことができました。その中で、特に印象に残ったのは「進路指導は、本人の希望を聞くだけではないよね。」との言葉です。確かに将来の進路選択において、本人の意向を大切にすることはもちろんですが、本人のことを客観的に理解できる他者としてアドバイスすることは教師の責務です。今ちょうど三者面談の期間中なので、この話題を職員朝会にて教職員に伝えました。
校長 皆藤正造
-
2025年7月16日(水)
大掃除で締めくくり
「校長のつぶやき」7月16日(水)
今日は登校した生徒による大掃除とロングホームルールがありました。私から生徒に対して話をする機会があり、今までの締めくくりとして伝えたことは以下の内容です。
1年生へ ・中学校時代にできなかったことにチャレンジしてほしい
・新しい出会いを大切にしてほしい
2年生 ・文化祭の打ち合わせの様子に感心した。秋の文化祭を期待している。
・高校生活が最も充実する時期、大切に過ごしてほしい。
3年生 ・進路選択で悩むだろうが、しっかり乗り越えてほしい。
・選挙権がある生徒は、投票にいこう。
全体 ・三者面談での担任からのアドバイスを大切に。
・誘惑に負けず、自分を大切に生活してほしい。
参加者による大掃除で、校舎内が一層きれいな環境になりました。その後のロングホームルームで学年職員からの指導を受け、午前中で生徒は下校しました。明日から7月30日までは三者面談の予定です。
※明日から夏休みになるので、校長のつぶやきはしばらくお休みします。学校行事等で話題があった際に随時掲載します。
校長 皆藤正造
-
2025年7月15日(火)
レポート締切日
「校長のつぶやき」7月15日(火)
今日は前期のスクーリング最終日で、7月のレポート締切日でもあります。毎月のレポート締切が近づくと職員室のカウンターに生徒たちが並んで先生たちに受けつけてもらいます。また、レポート締切日が近づくと、職員室で生徒へ電話連絡をする先生たちの声が聞こえてきます。そのやりとりを聞いていて、生徒を支えてくれる先生たちに頭が下がる思いで見守っています。頑張れ水戸平成学園高等学校の生徒たち!
校長 皆藤正造
-
2025年7月14日(月)
ハレとケを知る
「校長のつぶやき」7月14日(月)
7月11日(木)1時間目、家庭基礎・家庭総合の授業を参観した際、指導者の茂垣教頭先生が、「お正月やひな祭り、七五三や結婚式などの特別な日を日本では「ハレ」といいます。では、そうでない普段の日は何というか分かりますか。」との発問を耳にし、私も「はて?」と思いその後の続きを生徒と一緒に学びました。普段の日は「ケ」といい「ハレ」と区別するとのこと。授業の後、茂垣教頭先生から授業で取り扱った教科書のページを見せてもらいました。
・・・年中行事(正月など)や七五三、結婚披露宴などの人生の節目にあたる通過儀礼に用いる「ハレ」の日の食べ物を行事食といい、ハレの日に行事食を食べることには「邪気や災厄をはらい、健康長寿を願う」という意味がある。 日々の生活をハレ(非日常)とケ(日常)に分け、ハレの日には日常と異なった食事をする 東京書籍より一部抜粋・・・
校長 皆藤 正造
-
2025年7月11日(金)
人と対話する機会を増やす
「校長のつぶやき」7月11日(金)
過日の学校訪問の際、ある中学校の校長先生との懇談の中で、今の中学生の人間関係づくりについての話題になりました。校長先生の見立てでは、ちょっとしたことでつまづいてしまうケースがあり、コロナ禍で人と対話する機会が少なかったことが影響しているのではとのことでした。私も本校の上野公園遠足での3年生との会話でコロナ禍の影響は再認識しましたが、人と直接対話することでしか身につかないこともたくさんあります。本校でも、様々な機会に仲間と対話する場面を多く設定したいと考えています。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月10日(木)
水戸市内の学校訪問
「校長のつぶやき」7月10日(木)
昨日は茂垣教頭先生と一緒に水戸市内の中学校を訪問しました。各校の校長先生や、3学年主任、進路担当の先生方と懇談することができ、中学校の実情を知る上でも貴重な機会です。校則をなくして求める生徒像をお手本にしている学校、学区内にあらたな団地が造成され生徒の急増により校舎を増築する学校、部活動地域移行の難しさを伝えてくれた学校など、様々なお話を伺うことができました。こちらは、通信制高校の学びや本校の特色などを説明しています。今後も近隣の中学校との連携を深め、学校経営に反映していきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月9日(水)
月1回の学年会議から
「校長のつぶやき」7月9日(水)
本校では、毎月1回教職員よる学年会議を行っています。今月は、7月7日(月)に実施しました。これは各学年の生徒の状況等を共通理解し、指導に生かすためのものです。参加者は、校長 各学年職員 養護担当 進路担当 スクールカウンセラーが出席します。各学年の情報交換の後、スクールカウンセラーが新聞記事を資料として提供してくれました。児童精神科医の山口有紗氏の記事で、タイトルは「子どもの声 真剣に聞く社会に」です。その中で「子どもたちが信頼できる誰かとつながる安心感の中で傷を癒し、豊かに育っていけるよう願っています。そのためには、子どもたちの声を本当の意味で「聴く」ことが必要です。」が目にとまり、参加者に共有してもらいました。私を含めて、本校の教職員が子どもの話をきちんと受け止める大人でありたいと思います。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月8日(火)
人権教室・面接突破講座
「校長のつぶやき」7月8日(水)
7月7日(月)は、午前中に人権教室、午後には面接突破講座が行われました。人権教室は、水戸人権擁護委員協議会から2名の講師を招いて、「人権について考えよう」をテーマに2時間の講座でした。前半はこどもの権利条約についての学び、後半は「リスペクト・アザース」という内容で相手を尊重することのスキルを学びました。世の中の人たちすべてが居心地のよい社会になるために、これからの社会を担う若者たちに託す大切な時間でした。
午後の面接突破講座は、(株)「さんぽう」より専任の講師を3名招いて、大学進学、専門学校、就職の3つのコースに分かれて2時間の講座を行いました。就職の求人も7月から解禁となり、3年生にとっては進路選択の大切な時期となりました。教室を参観して印象に残ったことは、講師の「面接の際、ドアを開ける時の表情を大切にしよう。第一印象をよくするために、下を向いたりせずにしっかりと正面を向いて入りましょう。」との指導です。それぞれの教室では、個別の模擬面接が行われ、一人ひとりに細かいアドバイスがありました。参加者は、今日の講義を経て自覚を新たに前へ進んでほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年7月7日(月)
投票しないと罰金の国あり
「校長のつぶやき」7月7日(月)
先週の7月3日に参議院議員選挙が公示され、マスコミ等の報道も過熱しています。街中にも選挙ポスターが掲示され、7月20日の投票日に向けての選挙活動が始まりました。本校においても7月4日(金)の職員朝会にて、理事長から職員に対して投票を推奨する話があり、その中でオーストラリアの投票率が90%を超えていること、その理由は投票にいかないと罰金が課せられるという話がありました。本校の教職員はもちろん、本校の生徒で7月20日までに18歳に達する生徒には選挙権が与えられます。せっかくの権利を無駄にしないよう、投票所へ足を運んでほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年7月4日(金)
消しゴムのカスとシクラメンのつぼみ
「校長のつぶやき」7月4日(金)
本校では毎朝8時30分に職員朝会を行います。昨日は、ある職員から教室の机に残っている消しゴムのカスが気になるとの報告がありました。授業中に出た消しゴムのカスは床に落とさないで、机の上でまとめて捨てるのが本校のマナーです。また、日直の職員は朝会の最後にスピーチをすることになっており、スピーチから玄関に置いてあるシクラメンの鉢の1つにつぼみが出てきたことを教えてもらいました。朝会の後、さっそく玄関においてあるシクラメンの鉢からつぼみが1つあるのを見つけ、ちょっとした幸せな気分にひたりました。
校長 皆藤正造
-
2025年7月3日(木)
生徒に助けられたイモムシ
「校長のつぶやき」7月3日(木)
生徒の登校時と下校時は、校舎前に立って生徒一人ひとりに声をかけるようにしています。ここ数日は酷暑の日が続いているので、朝からの日差しが強くて汗をかきながら迎えています。昨日の朝バイクで登校した生徒が、バイクを駐輪場へ停めた後、正門付近で何かを手に載せて私に見せてくれました。その物体は直径1㎝メートルの立派(?)なイモムシでした。学校入り口のど真ん中にいたらしく、当日出入りした車に踏まれることなくいたようです。「どうします?」と問われたので、正門の植え込みを指して「あそこに離してあげたら」と返答ました。心優しい生徒に助けられ命拾いしたイモムシが、立派な蝶になってくれれば最高です。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月2日(水)
理科特別授業 JAXA見学・実験植物園
「校長のつぶやき」7月2日(水)
7月1日(火)に理科の特別授業が行われ、つくば市にある JAXAと筑波実験植物園の見学に行きました。参加した生徒は34名、引率は矢野先生と小張先生です。
JAXA見学では,国際宇宙ステーションの中にある日本の実験施設「きぼう」の地上管制室の見学をすることができました。また,筑波実験植物園では自然では絶滅してしまった植物など珍しい植物を観察することができました。本物に直接ふれる、見ることは生徒の学びを深めてくれたことと思います。校長 皆藤正造
-
2025年7月1日(火)
見つける 磨く 光をあてる
「校長のつぶやき」7月1日(火)
これは私の住む小美玉市のキャッチフレーズです。「小美玉」の由来は、小川町、美野里町、玉里村の3町村からとった名前ですが、このキャッチフレーズは「小さな美しい玉」をイメージして創作したようです。私はこの言葉が教育活動にぴったりのフレーズだと思い、日ごろの教職員の仕事ぶりや生徒の活動の様子を参観しています。自分の行動を認めてもらうことは、励みにつながります。水戸平成学園高等学校の教職員や生徒たちがさらに美しく輝くように微力ながらしっかり見て光をあてていきます。
校長 皆藤正造
-
2025年6月30日(月)
人間力を磨く
「校長のつぶやき」6月30日(月)
あるスポーツ新聞に掲載されていた、現在プロ野球で活躍している某選手の記事が目に留まりました。その選手は、高校野球の強豪 大阪桐蔭高校の出身で、西谷監督からの指導を紹介する中で、野球の技術指導よりも「人間力を磨くこと」を繰り返し指導されたようです。例えば、トイレのスリッパをきちんと揃えたりするなど、自分が周りに対してできることをきちんとやり抜くことのようです。本校の生徒たちも、自分を支えてくれる家族をはじめ、世の中に対して貢献することをとおして自分を磨いてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月27日(金)
自分事としてとらえる
「校長のつぶやき」6月27日(金)
名古屋市と横浜市の小学校教員が関係した盗撮事件の報道がここ数日続いています。事件の内容については、教育者としてあるまじき行為で言語道断です。本校としても、今回の事件を受けての未然防止について、今朝の職員朝会にて私から話をしました。「自分事としてとらえる」ということは、自分の学校で起こってまったら、どうすればよいのか。また、事件が起こらないようにするのはどうすればよかったのかを考えることです。学校関係者が、自分ができることを肝に命じて考え行動することが大切だと考えます。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月26日(木)
面接突破講座
「校長のつぶやき」6月26日(木)
6月25日(水)の午後、進路指導の特別講義「AO・推薦入試 面接突破講座」を実施しました。講師は、八文字学園学生支援センターの川上 勝様を招いて、面接試験の心構えや所作、準備等について具体的にポイントを押さえて指導いただきました。ここで、当日に使用したワークシートの一部を紹介します。 ※( )に生徒が正解を記入
「誰もができることができない」とは?
( 入室、退室 )の手順がわからない。
( 試験に見合わない )服装や着こなしをしている。
( 基本的な質問 )に答えられない。
面接に関することは、知っているかどうかです。参加した生徒たちが、今日の学びをこれからの受験等に生かしてほしいと願います。私も背広の第一ボタンを留めることが正しい身だしなみだということを、40代になるまで知りませんでした。
校長 皆藤正造
-
2025年6月25日(水)
「学校が明るいですね」
「校長のつぶやき」6月25日(水)
タイトルの言葉は、昨日学校説明に訪れた保護者の方のコメントです。本校では事前に連絡をいただければ、転入・編入等の相談を含めた学校説明を随時行っています。また、毎月の第2,第4土曜日(電話での予約が必要)にも行っています。本校の教員から学校の教育内容の説明の後に、校舎内を見学してもらいます。今回のコメントを頂いた方は、授業や多目的ルームでの生徒の様子をご覧になっての感想だったようです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月24日(火)
福を拾う
「校長のつぶやき」6月24日(火)
私の日課の1つは、昼休みに学校周辺の道路を歩きながの巡回です。その際に、ビニール袋を持ち、道路にゴミが落ちていれば拾うようにしています。大リーグで活躍している大谷翔平選手が、グラウンドでゴミを拾うことが報道された際に、高校時代から行っている習慣で、ゴミではなく「福を拾う」という意味での行動との内容だったと記憶しています。私は小美玉市に住んでいますが、道路の周辺は農地や雑木林が多く、ドライバーがビニール袋にため込んだゴミや空き缶、ペットボトルなどを道路脇に捨てることが頻繁です。そのままでは地域住民として見過ごせないので、犬の散歩やジョギングの合間にゴミを拾うようにしています。道路脇に落ちている福を拾い始めて10年近くになりますが、健康で毎日元気に仕事ができることが、福を拾っているわたしへのご利益だと思っています。
校長 皆藤正造
-
2025年6月23日(月)
大学教授による理科特別授業
「校長のつぶやき」6月23日(月)
6月20日(金)の午後、理科の特別授業「理科実験教室」が行われました。講師は日本工業大学 共通教育学群教授 服部邦彦先生をお招きしました。服部先生は、核融合の研究や惑星探査機「はやぶさ」の推進エンジンの研究に携わるなど、著名な研究者です。本校の国語担当 塙 雅文先生の教え子にあたり、塙先生の紹介で今回の特別授業が実現しました。当日の4、5時間を使っての特別授業でしたが、万有引力の法則や重心の解説等、模型を各自製作したりするなど高校生にもわかりやすく指導いただきました。授業の最後には、以前にテレビ放映されている「真空砲」の実験を見せていただきました。私も2時間の授業を参観させていただきましたが、科学の深さと広さを痛感しました。
授業の中で、服部先生が映像で紹介したコメントを紹介します。
校長 皆藤 正造
科学(物理)は覚えるものではない。
科学(物理)は不思議と思う好奇心と探究心である。
-
2025年6月20日(金)
進路セミナー・志望校決定ガイダンス
「校長のつぶやき」6月20日(金)
6月19日(木)は、午前中に第1回進路セミナー、午後に志望校決定ガイダンス・就職面接講座が行われました。
進路セミナーは原則を1年生対象とし、以下の職種について、それぞれの分野の専門学校から関係者を招いて希望する職種の説明や体験実習等がありました。
分野一覧
建築・土木 自動車 美容 フード ITマルチメディア 事務・経理 ホテル・ブライダル 公務員 幼児教育・保育 福祉 ファッション・デザイン 動物 エンターティメント 看護 理学療法・言語聴覚
午後の志望校決定ガイダンス・就職面接講座については、3年生と保護者を対象とし、生徒の希望があった大学9校と専門学校20校の関係者に来校いただきました。同時に、就職希望者対象に就職面接講座を行い、面接指導の専門講師から指導を受けました。
それぞれの生徒が、進路に関する有意義な情報を掴んで、進路選択に活かしてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月19日(木)
保育園ボランティア
「校長のつぶやき」6月19日(木)
昨日の午後2時30分から、本校JRC(青少年赤十字)部のボランティアとして、学校近くの「わかな保育園」での活動が実施されました。私も茂垣教頭先生と一緒に訪問して、園の関係者に挨拶させていただき、その後生徒たちと園児の様子を参観しました。当日は7名の生徒が参加し、おもいおもいに園児の遊び相手を努めていました。幼児とのふれあい体験は、参加した生徒たちにとっても貴重な経験になったはずです。今回の活動は今後も定期的に実施される予定です。なるべく多くの生徒に参加してほしいと願っています。
校長 皆藤正造
-
2025年6月18日(水)
学校訪問が始まる
「校長のつぶやき」6月18日(水)
今週から本校職員による中学校等への学校訪問が始まりました。県内の主な中学校や義務教育学校、教育支援センター等を訪問し、入学案内等について説明することがねらいです。昨日は、小美玉市内の学校や教育施設を郡司先生と一緒に訪問しました。美野里中学校、玉里学園義務教育学校、小川南中学校、小川北義務教育学校では、各校の校長先生方と懇談することができ、市内の教育支援センター2カ所(パステルおみたま ハーモニおみたま)でも、担当職員の方々にご挨拶することができました。今後も、都合のつく限り職員の学校訪問に同行し、中学校や関連施設等の状況を把握して本校の学校運営に反映できればと考えています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月17日(火)
図書室の紹介
「校長のつぶやき」6月17日(火)
本校の校舎1階の奥に図書室があります。書棚には文芸、新書、文庫本が並び、辞書や参考書も用意されています。また、「こころの本」「社会の本」「エッセイ、詩集」のコーナーもあります。部屋の奥には、個別の学習用デスクもあり、授業の合間に利用している生徒を見かけます。また、大学や専門学校の資料が並ぶ棚もあり、進路情報を把握するには最適な場所です。図書室の本については貸出等の制約がないので、気にいった本があれば自宅に持ち帰っても大丈夫です。生徒の皆さんには、ぜひ読書に興味を持ち、人との出会いと同じように、本との出会いを大切にしてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月16日(月)
消費生活セミナーから
「校長のつぶやき」6月16日(月)
6月13日(金)に、水戸市消費生活センター長 田山 知賀子様を講師に招いて、消費生活セミナーを実施しました。消費者問題の解説や、消費生活センターの相談事例の紹介、成年年齢引き下げによる18歳から可能になったことの解説など、若者がトラブルに巻き込まれないためのポイントを丁寧に教えてくさいました。私も、冒頭のあいさつの中で、20代の頃高額の英会話カセットを買わされそうになった苦い体験を紹介し、今日の学びを周りの知り合いにも広めてほしいことを伝えました。一番の願いは、人をおとしめて金を巻き上げるような人がいなくなる世の中になってほしいことです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月13日(金)
チーム学校・つかさどる
「校長のつぶやき」6月13日(金)
現在の望ましい学校づくりは、学校に勤務する職員がそれぞれの立場で連携しながら働くことが求められ、いわゆる「チーム学校」を目指します。先日の職員朝会にて、学校教育法に明記されている職務規定条項に使われている「つかさどる」という標記を例に、それぞれの立場で積極的に学校運営に参画してほしいことを話しました。本校の理事長 顧問 校長 教頭 教員 養護 事務職 相談員 運転手 26名それぞれが。自分の職務を自覚し、知恵を出し合い協力して「生きる力を育む学校」を推進します。
校長 皆藤正造
-
2025年6月12日(木)
「いわき 万本桜プロジェクト」
「校長のつぶやき」6月12日(木)
6月11日(水)は、本校の伝統行事「いわき 万本桜プロジェクト」へのボランティア参加の1回目が行われました。参加した生徒は27名、引率は、私と茂垣教頭先生、小張先生です。学校のバス2台に分乗し現地へ向かいました。いわき市の現地へ到着後、このプロジェクトを主催している志賀忠重さんから説明を受けて作業や昼食作りを行いました。このプロジェクトは、東日本大震災後の復興のために2011年の5月から開始されており、今まで多くのボランティアの協力を得て引き継がれているものです。本校は約10年前から活動に参加しており、年間3回(最後の回が桜の植樹)希望者を募っています。当日は、朝から雨が降り続いており、屋外での作業はできませんでしたが、羽釜をつかってご飯を炊き、カレーを作って参加者全員で昼食をとりました。また、プロジェクトを主催している志賀さんや、他のスタッフの方の体験談等を聞くことができ、参加した生徒(初めて参加した私もですが)貴重な体験になりました。
校長 皆藤正造
-
2025年6月11日(水)
「無敵な人」を作らない
「校長のつぶやき」6月11日(木)
毎朝通勤の車の中でラジオを聞いています。ある朝、DJが無敵な人をつくらないためにはどうしたらいいかというテーマでやりとりをしていました。「無敵な人」とは俗語で、いわゆる社会的に孤立していて、無差別殺人事件の容疑者になってしまうような人を指すようです。日々の報道で、何の関わりもなく事件に巻き込まれて命を落としてしまう事件を知るにつけ、何とも言えない気持ちになります。ラジオ番組での結論は、社会的に孤立しないような世の中のしくみが必要とのことでした。私たち一人ひとりが、できることをする。今の私の立場でやれることは、学校の教職員と一緒に、未来ある若者を支えていくこなのだとあらためて自覚しました。
校長 皆藤正造
-
2025年6月10日(火)
空気の質は学習の質に直結
「校長のつぶやき」6月10日(火)
「ドイツ人のすごい働き方 西村 栄基」を読んで、今すぐ自分たちの職場でも実践できることの事例があり、そのことを職員に説明しました。ドイツでは、オフィスの空気の質にも細心の注意が払われているらしく、多くの職場では、窓を開けて定期的に空気を入れ替えることが習慣となっているようです。
本校では、毎朝早く出勤する職員が校舎内の全教室の窓を開けてくれます。これからは、全職員で換気の大切さを共有し、定期的な空気の入れ替えを心がけます。
校長 皆藤正造
-
2025年6月9日(月)
コロナ禍を忘れない
「校長のつぶやき」6月9日(月)
6月6日(金)に春遠足が行われました。当日は75名の生徒が、東京の上野公園周辺を散策しました。学校からは、私と茂垣教頭先生、砂川先生が引率として同行しました。上野公園に到着後、動物園前で学年ごとに記念撮影をし、動物園に入園後に自由行動となりました。動物園内のベンチである3年生と会話していて、あらためて気づいたことがあります。3年生の中学校時代は、平成2年~4年でコロナ禍の真っ只中、学校生活で様々な制約があった時期でもあります。長い臨時休校、給食での黙食、部活動や校外活動の中止など、あげればきりがありません。高校2年生や1年生も、小学校や中学校時代に同様な制約を経験しています。私たち教育関係者は、今関わっている生徒たちが、コロナ禍の制約を受けてきていることを忘れてはならないとあらためて感じました。校長 皆藤正造
-
2025年6月6日(金)
韓国の投票率から
「校長のつぶやき」6月6日(金)
6月3日に韓国の大統領選挙があり、投票率が79.4%との報道がありました。私は選挙の際に投票所の立会人をすることもあり、選挙の投票率には特に関心があります。現在は18歳から選挙権が得られるので、本校の生徒たちの中には、今年7月に実施される参議院議員選挙の選挙権をもつ生徒も多いと思います。何事も最初が肝心ですので、選挙権がある生徒には必ず投票所に足を運んでほしいと思っています。選挙権を調べてみると、仮に7月20日が投票日だとすると、7月21日までに誕生日を迎える人(日本国民)が対象となるようです。選挙で投票することによって政治に参加する権利をきちんと行使する大人になってほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月5日(木)
長嶋茂雄の笑顔
「校長のつぶやき」6月5日(木)
ミスタープロ野球と称された長嶋茂雄さんが昨日亡くなりました。各テレビ局がニュースや特番で、彼の若かりし頃や選手、監督時代の映像が放映されました。その映像を見て私が感じたのは、彼の天真爛漫な人をひきつける笑顔でした。私も、子どもと接する仕事についてから心がけているのは、なるべく笑顔で接することです。
本校では、毎朝朝会で一日の行事予定等を確認しています。私から長嶋茂雄の笑顔を話題にし、「笑顔で生徒と接すること」を再確認しました。本校の教職員は皆素敵な笑顔で日ごろから生徒と接してくれているので、あくまでも確認でした。
校長 皆藤正造
-
2025年6月4日(水)
黒田 剛から学ぶ
「校長のつぶやき」6月4日(水)
高校サッカーの名将 黒田剛氏は、高校サッカー界から転身して、JリーグのFC町田ゼルビアの監督に就任し、1年でJ2を優勝に導きJ1昇格を果たし、すぐさまJ1で優勝争いにからむなど、顕著に活躍されている方です。
私が毎週購入している某週刊誌に、彼の記事が掲載されていました。その中に、黒田氏が青森山田高校の監督時代に、高校サッカー界の名将といわれる先輩の先生たちにサッカーの指導のことを相談すると、答えが皆ちがうこと。しかし、それぞれが信念を持ちブレることなく、自分に厳しく子どもたちとは真摯に向き合う姿勢は共通していたそうです。この記事を読んで、あらためて子どもを教育することに対する私の考えについて確認しました。私は「教育は負荷をかける営み」だと考えます。一人ひとりの生徒たちをどう成長させるか、教職員とともに考え実践していきます。校長 皆藤正造
-
2025年6月2日(月)
信じられる大人がいる学校
「校長のつぶやき」6月2日(月)
5月31日(土)に、本校の運営法人、栗村学園の理事会・評議員会が行われました。当日の評議員改選で、新たに本校の卒業生の方が加わりました。その方が会議中「当時、この学校に入って初めて大人って信じていいんだと思いました。」と発言されました。卒業生の方は開校当時に在籍し卒業されました。当時から丁寧な親身の指導が実践されており、脈々と受け継がれて本校の伝統になっています。
校長 皆藤正造
-
2025年5月28日(水)
花をかざる
「校長のつぶやき」5月28日(水)
私の自宅の庭に咲いている花を切り取って持参し、職員室のカウンターに飾っています。我が家には亡き父が手入れしていた樹木や草花があり今でも時期になると花を咲かせます。私自身も40代のころからガーデニングに興味を持ち、園芸店で珍しい草花の苗を見つけ、自宅で育てることがささやかな楽しみです。10年ぐらい前から自宅で咲いている花を職場に持っていき、飾るようになりました。本校に赴任後も続けており、最近は庭に咲き始めたカラーやシャクヤクを飾っています。花を飾ることの理屈はうまく表現できませんが、花を見ると心が和みます。学校の雰囲気づくりに少しでも役に立てれば幸いです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月27日(火)
授業 美術Ⅰから
「校長のつぶやき」5月27日(火)
5月25日(月)2・3時間目 美術Ⅰ(岩佐先生)の授業を参観しました。「絵の具を知ろう」という課題で、いろいろな絵の具とその特徴について学ぶ内容でした。
油絵の具、水彩絵の具、日本画の絵の具、アクリル絵の具の現物が用意されており、実際に着色した際の様子も直に観察することができました。日本画の絵の具のザラザラとした質感などは、私自身も初めての体験でした。また、油絵の具より前には「テンペラ画」が主流で、卵の卵黄を原料としていることや、かの有名なレオナルドダビンチ作「最後の晩餐」もその技法で描かれていることを学びました。
授業の後に、「モナリザ」はポプラの木の板に油彩で描かれているので顔料が剝がれやすく、もう2度とフランスから出せることが難しい(過去に2回ほど海外で展覧会があり、そのうちの1回が日本)と言われていることなども教えてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月26日(月)
可能性は口から始まる
「校長のつぶやき」5月26日(月)
5月23日(金)の1時間目 3学年合同のホームルームを参観しました。内容は、一般社団法人ハッシャダイソーシャルから派遣された講師の講話でした。派遣元のハッシャダイソーシャルは、高校や児童養護施設、少年院等を対象に講演活動に取り組んでいる団体です。昨年度もオンラインでの講話に協力してもらい、今年度は講師に直接来校してもらうことになりました。講師の大本観月(おおもと みずき)さんは、通信制高校を卒業後に、自動車関係の会社に就職し、その後ミュージカル俳優を経て現在に至っているとのことです。講話の中で、教訓となることばをいくつか示してくれました。タイトルの「可能性は口から始まる」はその中の1つで、やりたいことを自分の中にしまっておくだけでなく、言葉にすることによって、誰かが気がついてくれて動き出すことがあるとのこと。その他にも、大本さんの実体験から生まれた言葉をいくつも示してくれました。私自身、志の高い人間の話を聞き、刺激を受けた貴重な時間となりました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月23日(金)
電話でもLINEでも
「校長のつぶやき」5月23日(金)
昨日は、広島県福山市の通信制高校の事件を受けて、生徒たちへ緊急メッセージを発出しました。悩みがあったら一人で抱え込まないことを知ってもらうためです。私はこの3月まで茨城県教育委員会の生徒指導担当部署で働いていました。相談機関の運営や周知も仕事の1つでしたが、茨城県では30数年前から運営されている子ども(18歳までが対象)専用の電話相談機関「子どもホットライン」や、6年前から始まったLINEやWEBでの相談「いばらき子どもSNS相談」などがあります。他にも様々な行政機関や各種団体が相談窓口を開設しており、社会全体で子どもたちの悩みを受け止める体制が整っています。生徒の皆さん、苦しくても絶対に一人で悩まず、誰かに相談してください。
校長 皆藤正造
-
2025年5月22日(木)
特別活動・ひたち海浜公園BBQ
「校長のつぶやき」5月22日(木)
昨日、ひたち海浜公園にて特別活動の行事として、バーベキューを行いました。目的は新入生及び在校生のふれあいの場を作り、新しい友人をつくることとしています。生徒57名(1年生25名 2年生22名 3年生 10名)と職員が9名参加し、9つのグーループに分かれて実施しました。火起こしから始まり、鉄板を用意し、肉や野菜の食材を準備し、火が通った食材から食事をはじめ、最後のメニューは焼きそば、デザートには焼きマシュマロもあり、生徒たちにとって楽しい時間となったようです。
先日、来校した卒業生に水戸平成学園高等学校の良さを聞いたところ、「毎日スクーリングがあるし、特別活動が充実しています。」と答えてくれました。私にとって、卒業生の言葉を実感できた一日でした。
校長 皆藤正造
-
2025年5月22日(木)
学校からの緊急メッセージ
学校からの緊急メッセージ
昨日、広島県福山市の通信制高校にて、生徒が同じ学校の生徒3人をナイフで切りつけるという痛ましい事件が発生しました。事件の詳しいことはわかりませんが、事件を起こした生徒は、何かしら悩みを持っていたことかと思います。
皆さんも、いろいろな悩みがあると思いますが、苦しい時は一人で悩みを抱えることなく、誰かに相談してください。
相談する相手は、家族、学校の先生、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、自分の悩みを打ち明けられる相手なら誰でもいいです。また、電話相談やラインでの相談など、様々な相談機関もたくさんあります。
悩みは、人に話すことで小さくなります。生徒の皆さんは、悩みを1人で抱え込まないようにしてください。
令和7年5月22日
水戸平成学園高等学校 校長 皆藤正造
-
2025年5月21日(水)
授業 地理総合から
校長のつぶやき」5月21日(水) 授業 地理総合から
5月20日(火)2時間目 地理総合(矢野先生)の授業を参観しました。地理総合は必修科目であり、教科の内容は地理の一般常識が多く、就職試験等で問われることが多いそうです。
プリントの冒頭で生徒たちに課していた課題が、私自身も学び直しできたところでもありましたので、掲載いたします。
1 日本の人口(令和5年4月) 約1億2千500万人
2 日本を囲む4つの海の名称 太平洋 日本海 オホーツク海 東シナ海
3 世界の3つの大洋は 太平洋 大西洋 インド洋
4 世界の標準時は、どこの国を基準としたか イギリス
5 日本の標準時子午線はどこにあるか 兵庫県明石市 東経135°
授業終了後、私は職員室で矢野先生にいろいろ質問し、学ばせてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月21日(水)
授業 地理総合から
「校長のつぶやき」5月21日(水)
5月20日(火)2時間目 地理総合(矢野先生)の授業を参観しました。地理総合は必修科目であり、教科の内容は地理の一般常識が多く、就職試験等で問われることが多いそうです。
プリントの冒頭で生徒たちに課していた課題が、私自身も学び直しできたところでもありましたので、掲載いたします。
1 日本の人口(令和5年4月) 約1億2千500万人
2 日本を囲む4つの海の名称 太平洋 日本海 オホーツク海 東シナ海
3 世界の3つの大洋は 太平洋 大西洋 インド洋
4 世界の標準時は、どこの国を基準としたか イギリス
5 日本の標準時子午線はどこにあるか 兵庫県明石市 東経135°
授業終了後、私は職員室で矢野先生にいろいろ質問し、学ばせてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月20日(火)
職員会議から
「校長のつぶやき」5月20日(火)
5月19日(月)の午後4時15分から、職員会議がありました。毎月1度行われる会議で、翌月の行事等の確認をしています。
私からは、ある教育雑誌に掲載されていた「面倒見がよい大学」のランキングを紹介し、本校との共通点があるかどうか確認しました。
1位 金沢工業大学(私立 石川県) 20年連続1位 「学生を最大限に成長させることを組織的に行っている」「個々の学生に適した学習プログラムの提供」
2位 東北大学(国立 宮城県)「教員と学生の距離が近く、丁寧な指導が行われている。」
3位 武蔵大学(私立 東京)「1年次からゼミが必須、徹底した少人数教育」
4位 国際教養大学(公立 秋田県)「すべてが英語の少人数授業」「1年間の留学事務」
5位 福岡工業大学(私立 福岡県)「経営スローガンに For all the students」
上記の特徴を参考にしながら、生徒一人ひとりを多面的に理解し、丁寧な支援を通して生徒が成長できる学校を作ります。校長
皆藤正造
-
2025年5月19日(月)
熱心な先生たち
「校長のつぶやき」5月19日(月)
5月15日(木)の午後に、茨城県通信制高等学校等連絡協議会がオンラインで開催され、その中で午後3時からは第1回教員研修会がありました。本校からは、皆藤、茂垣教頭 郡司 植松が参加しました。今回の研修講師は、NHK学園高校の先生方4名で、テーマは「通信制高校における主体的・対話的な学び 協働的な学びの取り組み」でした。主な内容は、地学と地理 英語と音楽のコラボ授業 オンラインでの特別活動等の実践発表でした。発表後に質疑応答の時間になりましたが、真っ先に質問したのが茂垣教頭で、その後も各学校の先生方が次々と質問し、協議が約20分続きました。教育関係の研修会には数多く参加してきましたが、質問や意見が次々と出されて活発な協議となる研修会は稀です。県内の通信制高校は熱心な先生方が多いです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月15日(木)
自己を見つめよう
「校長のつぶやき」
私の学校での日課は、各教室で行われている授業を参観することです。内容によっては、私自身の学びにつながることも多くあり、一生徒になったつもりで、先生たちの言葉に耳を傾けます。
今日の1時間目、茂垣教頭先生による「家庭基礎 家庭総合」の授業の中で、「自己概念を高める」ことについて指導していました。自己概念とは自分について持っているイメージのことで、うまくいかない時でも自分は価値のある存在だと忘れないことが大切だそうです。教科書に「自分を見つめよう」として、3つの問いがありました。
1 自分の好きなところやプラス面を挙げよう。
2 今までに周囲の人(家族や友達、先生など)から褒められたことや感謝されたことを挙げよう。
3 自分が貢献していることについて考えよう。
皆さんも、この問いについて考えてみませんか。
校長 皆藤正造
-
2025年5月14日(水)
視野を広げる
「校長のつぶやき」5月14日(水)
本校は毎年、茨城キリスト教大学で心理学を学ぶ大学院生を心理実習生として迎えています。2年間の実習で、1年目は主に保健室での実習、2年目は個別の相談実習等も行います。
今日は、本年度から派遣される大学院生3名の初めての実習日なので、最初に私から実習の心構え等について話をしました。その際、心理学を大学で4年間学んできた学生さんたちなので、私から「レジリエンスを高めるために大切なこと」として質問を出し、回答を求めました。レジリエンスとはここ最近注目されてきた概念で、いわゆる「立ち直る力」「心のしなやかさ」のことを指します。どうすればレジリエンスを高めることができるか、ここ数年はいつも考えています。1人の実習生の回答は「視野を広げることかと思います。その時はつらいと感じたことも、時が経ってみると案外大丈夫なことがあるからです。」でした。私にとっては至極納得できる言葉でした。
校長 皆藤正造
-
2025年5月13日(火)
体育集中講義から
「校長のつぶやき」5月13日(火)
今日は体育集中講義があり、午前中がボウリング、 午後は千波湖ランニングを実施ました。午前中のボウリングは、水戸グリーンボウルを会場に46名が参加しました。平日の午前中でもあり、シニアの愛好会と思われる方たちが数組楽しんでおりました。本校から参加した生徒たちは、13のグループに分かれ和気あいあいとボウリングを楽しみました。
午後の千波湖ランニングは22名が参加しました。千波湖のランニングコース(1周3km)を2周するのが授業のノルマです。今日は気温が高く、熱中症が心配されましたが、幸い心地よい風がふいてくれたおかげで、全員が無事に完走・完歩することができました。
ある健康雑誌に、45分以上運動すると幸せホルモンが出ると記載があったので、私自身、意識的に体を動かすようにしています。今日は生徒たちの活動を直接見ながらたくさん運動できた一日でした。
校長 皆藤 正造
-
2025年5月13日(火)
環境は人をつくる
「校長のつぶやき」5月12日(月)
水戸平成学園に赴任して約1か月半が経ちました。毎朝職員は、出勤後に校舎内の分担(月ごとに変ります)を、掃き掃除やモップ掛けなどをしてから自分の仕事に取り掛かります。私も雑巾を絞って、職員室や近くの部屋のテーブルを拭いています。きれいな環境で生徒を迎えるための水戸平成学園高校の伝統です。教室の机やいすにも落書き等はまったくありません。生徒用の机の天板にいたってはピカピカの状態なので職員に聞くと、年度の終わりに必要に応じてニスを塗っているそうです。創立20年になりますが、大切にされてきた校舎をはじめきれいな環境で人を育てる学校です。
校長 皆藤正造
-
2025年5月10日(土)
自分を高める
「校長のつぶやき」5月10日(土)
今日は3学年対象の進路別合同説明会があり、午前中は大学進学希望の生徒と保護者、午後は専門学校希望の生徒と保護者が来校しました。進路指導担当の出沼教諭が、今後の見通しや確認事項等を説明しました。私は冒頭にあいさつさせていただきましたが、その際に生徒に伝えたことばが「自分を高める」です。
これからの将来は予測不能の社会になると言われています。いわゆる「いい学校を出て、いい会社に就職すれば安泰」ではなくなることは明らかです。ですから、これからの社会を担う人たちには、求められることが多々あるようです。大切なことは、いつも自分を高める気持ちを持って努力を重ねることではないでしょうか。この学校を巣立つ生徒たちには、様々な場面で私の思いを伝えていくつもりです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月9日(金)
誰といたか
「校長のつぶやき」5月8日
今日の5校時終了後、植松先生が指導する探究ゼミに参加した2年生16名が企画した、新入生対象のウエルカムパーティーが行われました。参加した2年生は、4月25日に事前打ち合わせを行い、3つのグループに分かれてレクリエーションを企画して今日を迎えました。1年生からは31名(本人の希望による)が参加し、2年生のリードで、新しい仲間と楽しい時間を過ごせたようです。
そもそも学校とは、同じくらいの年齢の子どもたちが一緒に時間を過ごす場所です。「何をしたか」よりも「誰といたか」を強く心に刻む場所なのかもしれません。水戸平成学園での出会いが新しい自分をつくるきっかけになることを願っています。「 校長 皆藤正造
-
2025年5月8日(木)
教育は人なり
「校長のつぶやき」5月8日
今日はスクーリング開始2日目です。生徒たちが2階の多目的ルームで談笑する光景を見ていると心が和みます。4月の学年ガイダンスで生徒たちに伝えましたが、高校時代は人生の中で最も自由を謳歌できる貴重な時です。平成学園の生徒たちが笑顔で毎日生活してほしいと願っています。
さて、本校の評判に関する2つ目の理由は、教師集団の力量の高さです。4月に赴任してから、教職員の働きぶりを見ていると気が付くことがあります。相手が保護者であっても生徒であっても、柔らかい言葉で丁寧に対応してくれています。本校には途中からの転入学相談が入ることが少なくありません。そのような場面では、どの教職員も親身の対応を心がけています。彼らはいつもと同じ対応をしているつもりだと思いますが、3月まで外にいた私の眼にはその丁寧ぶりは際立っています。平成学園の強みは、引き出しが多く心が広い教職員です。
校長 皆藤正造 -
2025年5月7日(水)
壁のない職員室
「校長のつぶやき」
このコーナーを利用して、学校生活を通して私が感じたことや在校生や保護者の皆様にお伝えたいことを掲載させていただきます。
4月に着任する以前から、水戸平成学園高校は「生徒への面倒見がいい学校」としての評判を耳にしていたので、そのワケを知ることを私自身へのミッションとしました。その1つとして「壁のない職員室」を挙げます。校舎に入って1階の中ほどに「職員室」があります。一般的な学校のように壁で仕切られているわけではなく、カウンターのような構造になっており、生徒たちは廊下から直接教員に声をかけることができますし、教員たちも登校してきた生徒へすぐ声をかけられます。この設計については、中村三喜前校長(現特別顧問)が携わったとのことです。本校の目指す学校像の1つ「教師と生徒のface to face」の実践に繋がっていることは間違いありません。
校長 皆藤正造 -
2025年1月22日(水)
「茨城いのちの電話」への寄付金
本校生徒の皆さんは、学校の自販機で飲み物を買ったことはありますか?
実は、売り上げの一部が社会福祉事業のための寄付金にあてられています。
この度、2024年の寄付金「36,660円」に対するお礼が「社会福祉法人 茨城いのちの電話」より届きましたので報告いたします。
次に自販機で飲み物を買う際には、自分の行動が誰かのためになっていることを思い出してもらえると嬉しく思います!
リンク:茨城いのちの電話HP -
2025年1月21日(火)
茨城新聞文化福祉事業団による「愛の募金」~12/29 茨城新聞~
茨城新聞文化福祉事業団による「愛の募金」についての記事が茨城新聞に掲載されました。寄付の際には、文化祭実行委員長の小沼翔太さん(2学年)が代表として茨城新聞社を訪問しました。

-
2024年8月14日(水)
8.14(水)原風景
2024年8月14日(水)
生徒の皆さんへ
「原風景」
私は1944年の生まれですので、今月19日を迎えると満80歳になります。そして、それはお盆の時季でもあるので、久しぶりに昔よく通った道や遊んだ場所を歩いてみると、幼い頃の記憶がよみがえり、懐かしさや、すっかり変わってしまった風景への哀惜、もう二度とあの頃には戻れないのだという寂しさなど、さまざまな思いがこみ上げてくる。
同時に、家族や友だち、その時身近にいてくれた人たちの姿や言葉が思い出されて、それらが自分の物の見方や考え方の原点になり、今日まで折々に支えとなってきたことに改めて気づかされる。
変わりゆく時代の中で、人は時に過去をたどり、いつまでも変わらない自らの原風景に立つ。そうすることで自分を確かめ、明日に希望をつないで、新たな人生を紡いでゆけるのだろう。
そして、自分の生きた証もまた決して消えることなく、必ず誰かの心の風景に刻まれてゆくはずである。できることなら、その人が苦しいとき、迷ったときに立ち返る拠り所となって、勇気を与えられるような、そんな生き方をしてゆきたい。
周囲の大切な人たちの心に、自分はどんな風景を残すことができるのだろうか。校長 中村三喜
-
2024年4月9日(火)
校長より生徒の皆さんへ【第18回】
校長より生徒の皆さんに第18回目の言葉です。
2024年4月9日(火)
生徒の皆さんへ
「新しい夢」
今の小学生に将来の夢として、なりたい職業を尋ねると、男の子ならプロスポーツ選手やゲームクリエーター、女の子なら保育士、医師、パティシエといった答えが返ってくるという。時代の違いはあるけれど、子供達の夢はいたって明快、語らう姿を想像するだけでも微笑(ほほえ)ましい。
ところが夢のとおり叶うかはさておき、大人になって職に就き、幾春秋が過ぎるうちに、いつしか新しい夢を持たなくなってしまう。
いやいや仕事には常に目標があり、目標を達成すればまた次の目標が与えられ、倦(う)むことはない。そう言い切れるならばそれはそれで結構なことだ。
とはいえ、目標は一つの目安にすぎない。まして目標達成のために汲々(きゅうきゅう)とし、真の仕事の喜びや自分を高める楽しさを見失ってはつまらない。
仕事に限らず、いつも夢を持ち続けよう。日常の些事(さじ)に追われて疲れを覚えても、夢を思い起こせば元気が戻ってくる。
人生は夢あればこそ輝くことを忘れないでいたい。
校長 中村三喜