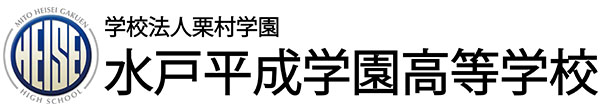保護者の皆様,在校生へ
学校から在校生の皆さまへのお知らせを掲載します。
-
2025年7月16日(水) [NEW]
大掃除で締めくくり
「校長のつぶやき」7月16日(水)
今日は登校した生徒による大掃除とロングホームルールがありました。私から生徒に対して話をする機会があり、今までの締めくくりとして伝えたことは以下の内容です。
1年生へ ・中学校時代にできなかったことにチャレンジしてほしい
・新しい出会いを大切にしてほしい
2年生 ・文化祭の打ち合わせの様子に感心した。秋の文化祭を期待している。
・高校生活が最も充実する時期、大切に過ごしてほしい。
3年生 ・進路選択で悩むだろうが、しっかり乗り越えてほしい。
・選挙権がある生徒は、投票にいこう。
全体 ・三者面談での担任からのアドバイスを大切に。
・誘惑に負けず、自分を大切に生活してほしい。
参加者による大掃除で、校舎内が一層きれいな環境になりました。その後のロングホームルームで学年職員からの指導を受け、午前中で生徒は下校しました。明日から7月30日までは三者面談の予定です。
※明日から夏休みになるので、校長のつぶやきはしばらくお休みします。学校行事等で話題があった際に随時掲載します。
校長 皆藤正造
-
2025年7月15日(火) [NEW]
レポート締切日
「校長のつぶやき」7月15日(火)
今日は前期のスクーリング最終日で、7月のレポート締切日でもあります。毎月のレポート締切が近づくと職員室のカウンターに生徒たちが並んで先生たちに受けつけてもらいます。また、レポート締切日が近づくと、職員室で生徒へ電話連絡をする先生たちの声が聞こえてきます。そのやりとりを聞いていて、生徒を支えてくれる先生たちに頭が下がる思いで見守っています。頑張れ水戸平成学園高等学校の生徒たち!
校長 皆藤正造
-
2025年7月14日(月) [NEW]
ハレとケを知る
「校長のつぶやき」7月14日(月)
7月11日(木)1時間目、家庭基礎・家庭総合の授業を参観した際、指導者の茂垣教頭先生が、「お正月やひな祭り、七五三や結婚式などの特別な日を日本では「ハレ」といいます。では、そうでない普段の日は何というか分かりますか。」との発問を耳にし、私も「はて?」と思いその後の続きを生徒と一緒に学びました。普段の日は「ケ」といい「ハレ」と区別するとのこと。授業の後、茂垣教頭先生から授業で取り扱った教科書のページを見せてもらいました。
・・・年中行事(正月など)や七五三、結婚披露宴などの人生の節目にあたる通過儀礼に用いる「ハレ」の日の食べ物を行事食といい、ハレの日に行事食を食べることには「邪気や災厄をはらい、健康長寿を願う」という意味がある。 日々の生活をハレ(非日常)とケ(日常)に分け、ハレの日には日常と異なった食事をする 東京書籍より一部抜粋・・・
校長 皆藤 正造
-
2025年7月11日(金) [NEW]
人と対話する機会を増やす
「校長のつぶやき」7月11日(金)
過日の学校訪問の際、ある中学校の校長先生との懇談の中で、今の中学生の人間関係づくりについての話題になりました。校長先生の見立てでは、ちょっとしたことでつまづいてしまうケースがあり、コロナ禍で人と対話する機会が少なかったことが影響しているのではとのことでした。私も本校の上野公園遠足での3年生との会話でコロナ禍の影響は再認識しましたが、人と直接対話することでしか身につかないこともたくさんあります。本校でも、様々な機会に仲間と対話する場面を多く設定したいと考えています。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月10日(木) [NEW]
水戸市内の学校訪問
「校長のつぶやき」7月10日(木)
昨日は茂垣教頭先生と一緒に水戸市内の中学校を訪問しました。各校の校長先生や、3学年主任、進路担当の先生方と懇談することができ、中学校の実情を知る上でも貴重な機会です。校則をなくして求める生徒像をお手本にしている学校、学区内にあらたな団地が造成され生徒の急増により校舎を増築する学校、部活動地域移行の難しさを伝えてくれた学校など、様々なお話を伺うことができました。こちらは、通信制高校の学びや本校の特色などを説明しています。今後も近隣の中学校との連携を深め、学校経営に反映していきます。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月9日(水) [NEW]
月1回の学年会議から
「校長のつぶやき」7月9日(水)
本校では、毎月1回教職員よる学年会議を行っています。今月は、7月7日(月)に実施しました。これは各学年の生徒の状況等を共通理解し、指導に生かすためのものです。参加者は、校長 各学年職員 養護担当 進路担当 スクールカウンセラーが出席します。各学年の情報交換の後、スクールカウンセラーが新聞記事を資料として提供してくれました。児童精神科医の山口有紗氏の記事で、タイトルは「子どもの声 真剣に聞く社会に」です。その中で「子どもたちが信頼できる誰かとつながる安心感の中で傷を癒し、豊かに育っていけるよう願っています。そのためには、子どもたちの声を本当の意味で「聴く」ことが必要です。」が目にとまり、参加者に共有してもらいました。私を含めて、本校の教職員が子どもの話をきちんと受け止める大人でありたいと思います。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月8日(火) [NEW]
人権教室・面接突破講座
「校長のつぶやき」7月8日(水)
7月7日(月)は、午前中に人権教室、午後には面接突破講座が行われました。人権教室は、水戸人権擁護委員協議会から2名の講師を招いて、「人権について考えよう」をテーマに2時間の講座でした。前半はこどもの権利条約についての学び、後半は「リスペクト・アザース」という内容で相手を尊重することのスキルを学びました。世の中の人たちすべてが居心地のよい社会になるために、これからの社会を担う若者たちに託す大切な時間でした。
午後の面接突破講座は、(株)「さんぽう」より専任の講師を3名招いて、大学進学、専門学校、就職の3つのコースに分かれて2時間の講座を行いました。就職の求人も7月から解禁となり、3年生にとっては進路選択の大切な時期となりました。教室を参観して印象に残ったことは、講師の「面接の際、ドアを開ける時の表情を大切にしよう。第一印象をよくするために、下を向いたりせずにしっかりと正面を向いて入りましょう。」との指導です。それぞれの教室では、個別の模擬面接が行われ、一人ひとりに細かいアドバイスがありました。参加者は、今日の講義を経て自覚を新たに前へ進んでほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年7月7日(月) [NEW]
投票しないと罰金の国あり
「校長のつぶやき」7月7日(月)
先週の7月3日に参議院議員選挙が公示され、マスコミ等の報道も過熱しています。街中にも選挙ポスターが掲示され、7月20日の投票日に向けての選挙活動が始まりました。本校においても7月4日(金)の職員朝会にて、理事長から職員に対して投票を推奨する話があり、その中でオーストラリアの投票率が90%を超えていること、その理由は投票にいかないと罰金が課せられるという話がありました。本校の教職員はもちろん、本校の生徒で7月20日までに18歳に達する生徒には選挙権が与えられます。せっかくの権利を無駄にしないよう、投票所へ足を運んでほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年7月4日(金) [NEW]
消しゴムのカスとシクラメンのつぼみ
「校長のつぶやき」7月4日(金)
本校では毎朝8時30分に職員朝会を行います。昨日は、ある職員から教室の机に残っている消しゴムのカスが気になるとの報告がありました。授業中に出た消しゴムのカスは床に落とさないで、机の上でまとめて捨てるのが本校のマナーです。また、日直の職員は朝会の最後にスピーチをすることになっており、スピーチから玄関に置いてあるシクラメンの鉢の1つにつぼみが出てきたことを教えてもらいました。朝会の後、さっそく玄関においてあるシクラメンの鉢からつぼみが1つあるのを見つけ、ちょっとした幸せな気分にひたりました。
校長 皆藤正造
-
2025年7月3日(木) [NEW]
生徒に助けられたイモムシ
「校長のつぶやき」7月3日(木)
生徒の登校時と下校時は、校舎前に立って生徒一人ひとりに声をかけるようにしています。ここ数日は酷暑の日が続いているので、朝からの日差しが強くて汗をかきながら迎えています。昨日の朝バイクで登校した生徒が、バイクを駐輪場へ停めた後、正門付近で何かを手に載せて私に見せてくれました。その物体は直径1㎝メートルの立派(?)なイモムシでした。学校入り口のど真ん中にいたらしく、当日出入りした車に踏まれることなくいたようです。「どうします?」と問われたので、正門の植え込みを指して「あそこに離してあげたら」と返答ました。心優しい生徒に助けられ命拾いしたイモムシが、立派な蝶になってくれれば最高です。
校長 皆藤 正造
-
2025年7月2日(水) [NEW]
理科特別授業 JAXA見学・実験植物園
「校長のつぶやき」7月2日(水)
7月1日(火)に理科の特別授業が行われ、つくば市にある JAXAと筑波実験植物園の見学に行きました。参加した生徒は34名、引率は矢野先生と小張先生です。
JAXA見学では,国際宇宙ステーションの中にある日本の実験施設「きぼう」の地上管制室の見学をすることができました。また,筑波実験植物園では自然では絶滅してしまった植物など珍しい植物を観察することができました。本物に直接ふれる、見ることは生徒の学びを深めてくれたことと思います。校長 皆藤正造
-
2025年7月1日(火) [NEW]
見つける 磨く 光をあてる
「校長のつぶやき」7月1日(火)
これは私の住む小美玉市のキャッチフレーズです。「小美玉」の由来は、小川町、美野里町、玉里村の3町村からとった名前ですが、このキャッチフレーズは「小さな美しい玉」をイメージして創作したようです。私はこの言葉が教育活動にぴったりのフレーズだと思い、日ごろの教職員の仕事ぶりや生徒の活動の様子を参観しています。自分の行動を認めてもらうことは、励みにつながります。水戸平成学園高等学校の教職員や生徒たちがさらに美しく輝くように微力ながらしっかり見て光をあてていきます。
校長 皆藤正造
-
2025年6月30日(月) [NEW]
人間力を磨く
「校長のつぶやき」6月30日(月)
あるスポーツ新聞に掲載されていた、現在プロ野球で活躍している某選手の記事が目に留まりました。その選手は、高校野球の強豪 大阪桐蔭高校の出身で、西谷監督からの指導を紹介する中で、野球の技術指導よりも「人間力を磨くこと」を繰り返し指導されたようです。例えば、トイレのスリッパをきちんと揃えたりするなど、自分が周りに対してできることをきちんとやり抜くことのようです。本校の生徒たちも、自分を支えてくれる家族をはじめ、世の中に対して貢献することをとおして自分を磨いてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月27日(金) [NEW]
自分事としてとらえる
「校長のつぶやき」6月27日(金)
名古屋市と横浜市の小学校教員が関係した盗撮事件の報道がここ数日続いています。事件の内容については、教育者としてあるまじき行為で言語道断です。本校としても、今回の事件を受けての未然防止について、今朝の職員朝会にて私から話をしました。「自分事としてとらえる」ということは、自分の学校で起こってまったら、どうすればよいのか。また、事件が起こらないようにするのはどうすればよかったのかを考えることです。学校関係者が、自分ができることを肝に命じて考え行動することが大切だと考えます。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月26日(木) [NEW]
面接突破講座
「校長のつぶやき」6月26日(木)
6月25日(水)の午後、進路指導の特別講義「AO・推薦入試 面接突破講座」を実施しました。講師は、八文字学園学生支援センターの川上 勝様を招いて、面接試験の心構えや所作、準備等について具体的にポイントを押さえて指導いただきました。ここで、当日に使用したワークシートの一部を紹介します。 ※( )に生徒が正解を記入
「誰もができることができない」とは?
( 入室、退室 )の手順がわからない。
( 試験に見合わない )服装や着こなしをしている。
( 基本的な質問 )に答えられない。
面接に関することは、知っているかどうかです。参加した生徒たちが、今日の学びをこれからの受験等に生かしてほしいと願います。私も背広の第一ボタンを留めることが正しい身だしなみだということを、40代になるまで知りませんでした。
校長 皆藤正造
-
2025年6月25日(水) [NEW]
「学校が明るいですね」
「校長のつぶやき」6月25日(水)
タイトルの言葉は、昨日学校説明に訪れた保護者の方のコメントです。本校では事前に連絡をいただければ、転入・編入等の相談を含めた学校説明を随時行っています。また、毎月の第2,第4土曜日(電話での予約が必要)にも行っています。本校の教員から学校の教育内容の説明の後に、校舎内を見学してもらいます。今回のコメントを頂いた方は、授業や多目的ルームでの生徒の様子をご覧になっての感想だったようです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月24日(火) [NEW]
福を拾う
「校長のつぶやき」6月24日(火)
私の日課の1つは、昼休みに学校周辺の道路を歩きながの巡回です。その際に、ビニール袋を持ち、道路にゴミが落ちていれば拾うようにしています。大リーグで活躍している大谷翔平選手が、グラウンドでゴミを拾うことが報道された際に、高校時代から行っている習慣で、ゴミではなく「福を拾う」という意味での行動との内容だったと記憶しています。私は小美玉市に住んでいますが、道路の周辺は農地や雑木林が多く、ドライバーがビニール袋にため込んだゴミや空き缶、ペットボトルなどを道路脇に捨てることが頻繁です。そのままでは地域住民として見過ごせないので、犬の散歩やジョギングの合間にゴミを拾うようにしています。道路脇に落ちている福を拾い始めて10年近くになりますが、健康で毎日元気に仕事ができることが、福を拾っているわたしへのご利益だと思っています。
校長 皆藤正造
-
2025年6月23日(月) [NEW]
大学教授による理科特別授業
「校長のつぶやき」6月23日(月)
6月20日(金)の午後、理科の特別授業「理科実験教室」が行われました。講師は日本工業大学 共通教育学群教授 服部邦彦先生をお招きしました。服部先生は、核融合の研究や惑星探査機「はやぶさ」の推進エンジンの研究に携わるなど、著名な研究者です。本校の国語担当 塙 雅文先生の教え子にあたり、塙先生の紹介で今回の特別授業が実現しました。当日の4、5時間を使っての特別授業でしたが、万有引力の法則や重心の解説等、模型を各自製作したりするなど高校生にもわかりやすく指導いただきました。授業の最後には、以前にテレビ放映されている「真空砲」の実験を見せていただきました。私も2時間の授業を参観させていただきましたが、科学の深さと広さを痛感しました。
授業の中で、服部先生が映像で紹介したコメントを紹介します。
校長 皆藤 正造
科学(物理)は覚えるものではない。
科学(物理)は不思議と思う好奇心と探究心である。
-
2025年6月20日(金) [NEW]
進路セミナー・志望校決定ガイダンス
「校長のつぶやき」6月20日(金)
6月19日(木)は、午前中に第1回進路セミナー、午後に志望校決定ガイダンス・就職面接講座が行われました。
進路セミナーは原則を1年生対象とし、以下の職種について、それぞれの分野の専門学校から関係者を招いて希望する職種の説明や体験実習等がありました。
分野一覧
建築・土木 自動車 美容 フード ITマルチメディア 事務・経理 ホテル・ブライダル 公務員 幼児教育・保育 福祉 ファッション・デザイン 動物 エンターティメント 看護 理学療法・言語聴覚
午後の志望校決定ガイダンス・就職面接講座については、3年生と保護者を対象とし、生徒の希望があった大学9校と専門学校20校の関係者に来校いただきました。同時に、就職希望者対象に就職面接講座を行い、面接指導の専門講師から指導を受けました。
それぞれの生徒が、進路に関する有意義な情報を掴んで、進路選択に活かしてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月19日(木) [NEW]
保育園ボランティア
「校長のつぶやき」6月19日(木)
昨日の午後2時30分から、本校JRC(青少年赤十字)部のボランティアとして、学校近くの「わかな保育園」での活動が実施されました。私も茂垣教頭先生と一緒に訪問して、園の関係者に挨拶させていただき、その後生徒たちと園児の様子を参観しました。当日は7名の生徒が参加し、おもいおもいに園児の遊び相手を努めていました。幼児とのふれあい体験は、参加した生徒たちにとっても貴重な経験になったはずです。今回の活動は今後も定期的に実施される予定です。なるべく多くの生徒に参加してほしいと願っています。
校長 皆藤正造
-
2025年6月18日(水)
学校訪問が始まる
「校長のつぶやき」6月18日(水)
今週から本校職員による中学校等への学校訪問が始まりました。県内の主な中学校や義務教育学校、教育支援センター等を訪問し、入学案内等について説明することがねらいです。昨日は、小美玉市内の学校や教育施設を郡司先生と一緒に訪問しました。美野里中学校、玉里学園義務教育学校、小川南中学校、小川北義務教育学校では、各校の校長先生方と懇談することができ、市内の教育支援センター2カ所(パステルおみたま ハーモニおみたま)でも、担当職員の方々にご挨拶することができました。今後も、都合のつく限り職員の学校訪問に同行し、中学校や関連施設等の状況を把握して本校の学校運営に反映できればと考えています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月17日(火)
図書室の紹介
「校長のつぶやき」6月17日(火)
本校の校舎1階の奥に図書室があります。書棚には文芸、新書、文庫本が並び、辞書や参考書も用意されています。また、「こころの本」「社会の本」「エッセイ、詩集」のコーナーもあります。部屋の奥には、個別の学習用デスクもあり、授業の合間に利用している生徒を見かけます。また、大学や専門学校の資料が並ぶ棚もあり、進路情報を把握するには最適な場所です。図書室の本については貸出等の制約がないので、気にいった本があれば自宅に持ち帰っても大丈夫です。生徒の皆さんには、ぜひ読書に興味を持ち、人との出会いと同じように、本との出会いを大切にしてほしいと願っています。
校長 皆藤 正造
-
2025年6月16日(月)
消費生活セミナーから
「校長のつぶやき」6月16日(月)
6月13日(金)に、水戸市消費生活センター長 田山 知賀子様を講師に招いて、消費生活セミナーを実施しました。消費者問題の解説や、消費生活センターの相談事例の紹介、成年年齢引き下げによる18歳から可能になったことの解説など、若者がトラブルに巻き込まれないためのポイントを丁寧に教えてくさいました。私も、冒頭のあいさつの中で、20代の頃高額の英会話カセットを買わされそうになった苦い体験を紹介し、今日の学びを周りの知り合いにも広めてほしいことを伝えました。一番の願いは、人をおとしめて金を巻き上げるような人がいなくなる世の中になってほしいことです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月13日(金)
チーム学校・つかさどる
「校長のつぶやき」6月13日(金)
現在の望ましい学校づくりは、学校に勤務する職員がそれぞれの立場で連携しながら働くことが求められ、いわゆる「チーム学校」を目指します。先日の職員朝会にて、学校教育法に明記されている職務規定条項に使われている「つかさどる」という標記を例に、それぞれの立場で積極的に学校運営に参画してほしいことを話しました。本校の理事長 顧問 校長 教頭 教員 養護 事務職 相談員 運転手 26名それぞれが。自分の職務を自覚し、知恵を出し合い協力して「生きる力を育む学校」を推進します。
校長 皆藤正造
-
2025年6月12日(木)
「いわき 万本桜プロジェクト」
「校長のつぶやき」6月12日(木)
6月11日(水)は、本校の伝統行事「いわき 万本桜プロジェクト」へのボランティア参加の1回目が行われました。参加した生徒は27名、引率は、私と茂垣教頭先生、小張先生です。学校のバス2台に分乗し現地へ向かいました。いわき市の現地へ到着後、このプロジェクトを主催している志賀忠重さんから説明を受けて作業や昼食作りを行いました。このプロジェクトは、東日本大震災後の復興のために2011年の5月から開始されており、今まで多くのボランティアの協力を得て引き継がれているものです。本校は約10年前から活動に参加しており、年間3回(最後の回が桜の植樹)希望者を募っています。当日は、朝から雨が降り続いており、屋外での作業はできませんでしたが、羽釜をつかってご飯を炊き、カレーを作って参加者全員で昼食をとりました。また、プロジェクトを主催している志賀さんや、他のスタッフの方の体験談等を聞くことができ、参加した生徒(初めて参加した私もですが)貴重な体験になりました。
校長 皆藤正造
-
2025年6月11日(水)
「無敵な人」を作らない
「校長のつぶやき」6月11日(木)
毎朝通勤の車の中でラジオを聞いています。ある朝、DJが無敵な人をつくらないためにはどうしたらいいかというテーマでやりとりをしていました。「無敵な人」とは俗語で、いわゆる社会的に孤立していて、無差別殺人事件の容疑者になってしまうような人を指すようです。日々の報道で、何の関わりもなく事件に巻き込まれて命を落としてしまう事件を知るにつけ、何とも言えない気持ちになります。ラジオ番組での結論は、社会的に孤立しないような世の中のしくみが必要とのことでした。私たち一人ひとりが、できることをする。今の私の立場でやれることは、学校の教職員と一緒に、未来ある若者を支えていくこなのだとあらためて自覚しました。
校長 皆藤正造
-
2025年6月10日(火)
空気の質は学習の質に直結
「校長のつぶやき」6月10日(火)
「ドイツ人のすごい働き方 西村 栄基」を読んで、今すぐ自分たちの職場でも実践できることの事例があり、そのことを職員に説明しました。ドイツでは、オフィスの空気の質にも細心の注意が払われているらしく、多くの職場では、窓を開けて定期的に空気を入れ替えることが習慣となっているようです。
本校では、毎朝早く出勤する職員が校舎内の全教室の窓を開けてくれます。これからは、全職員で換気の大切さを共有し、定期的な空気の入れ替えを心がけます。
校長 皆藤正造
-
2025年6月9日(月)
コロナ禍を忘れない
「校長のつぶやき」6月9日(月)
6月6日(金)に春遠足が行われました。当日は75名の生徒が、東京の上野公園周辺を散策しました。学校からは、私と茂垣教頭先生、砂川先生が引率として同行しました。上野公園に到着後、動物園前で学年ごとに記念撮影をし、動物園に入園後に自由行動となりました。動物園内のベンチである3年生と会話していて、あらためて気づいたことがあります。3年生の中学校時代は、平成2年~4年でコロナ禍の真っ只中、学校生活で様々な制約があった時期でもあります。長い臨時休校、給食での黙食、部活動や校外活動の中止など、あげればきりがありません。高校2年生や1年生も、小学校や中学校時代に同様な制約を経験しています。私たち教育関係者は、今関わっている生徒たちが、コロナ禍の制約を受けてきていることを忘れてはならないとあらためて感じました。校長 皆藤正造
-
2025年6月6日(金)
韓国の投票率から
「校長のつぶやき」6月6日(金)
6月3日に韓国の大統領選挙があり、投票率が79.4%との報道がありました。私は選挙の際に投票所の立会人をすることもあり、選挙の投票率には特に関心があります。現在は18歳から選挙権が得られるので、本校の生徒たちの中には、今年7月に実施される参議院議員選挙の選挙権をもつ生徒も多いと思います。何事も最初が肝心ですので、選挙権がある生徒には必ず投票所に足を運んでほしいと思っています。選挙権を調べてみると、仮に7月20日が投票日だとすると、7月21日までに誕生日を迎える人(日本国民)が対象となるようです。選挙で投票することによって政治に参加する権利をきちんと行使する大人になってほしいです。
校長 皆藤正造
-
2025年6月5日(木)
長嶋茂雄の笑顔
「校長のつぶやき」6月5日(木)
ミスタープロ野球と称された長嶋茂雄さんが昨日亡くなりました。各テレビ局がニュースや特番で、彼の若かりし頃や選手、監督時代の映像が放映されました。その映像を見て私が感じたのは、彼の天真爛漫な人をひきつける笑顔でした。私も、子どもと接する仕事についてから心がけているのは、なるべく笑顔で接することです。
本校では、毎朝朝会で一日の行事予定等を確認しています。私から長嶋茂雄の笑顔を話題にし、「笑顔で生徒と接すること」を再確認しました。本校の教職員は皆素敵な笑顔で日ごろから生徒と接してくれているので、あくまでも確認でした。
校長 皆藤正造
-
2025年6月4日(水)
黒田 剛から学ぶ
「校長のつぶやき」6月4日(水)
高校サッカーの名将 黒田剛氏は、高校サッカー界から転身して、JリーグのFC町田ゼルビアの監督に就任し、1年でJ2を優勝に導きJ1昇格を果たし、すぐさまJ1で優勝争いにからむなど、顕著に活躍されている方です。
私が毎週購入している某週刊誌に、彼の記事が掲載されていました。その中に、黒田氏が青森山田高校の監督時代に、高校サッカー界の名将といわれる先輩の先生たちにサッカーの指導のことを相談すると、答えが皆ちがうこと。しかし、それぞれが信念を持ちブレることなく、自分に厳しく子どもたちとは真摯に向き合う姿勢は共通していたそうです。この記事を読んで、あらためて子どもを教育することに対する私の考えについて確認しました。私は「教育は負荷をかける営み」だと考えます。一人ひとりの生徒たちをどう成長させるか、教職員とともに考え実践していきます。校長 皆藤正造
-
2025年6月2日(月)
信じられる大人がいる学校
「校長のつぶやき」6月2日(月)
5月31日(土)に、本校の運営法人、栗村学園の理事会・評議員会が行われました。当日の評議員改選で、新たに本校の卒業生の方が加わりました。その方が会議中「当時、この学校に入って初めて大人って信じていいんだと思いました。」と発言されました。卒業生の方は開校当時に在籍し卒業されました。当時から丁寧な親身の指導が実践されており、脈々と受け継がれて本校の伝統になっています。
校長 皆藤正造
-
2025年5月28日(水)
花をかざる
「校長のつぶやき」5月28日(水)
私の自宅の庭に咲いている花を切り取って持参し、職員室のカウンターに飾っています。我が家には亡き父が手入れしていた樹木や草花があり今でも時期になると花を咲かせます。私自身も40代のころからガーデニングに興味を持ち、園芸店で珍しい草花の苗を見つけ、自宅で育てることがささやかな楽しみです。10年ぐらい前から自宅で咲いている花を職場に持っていき、飾るようになりました。本校に赴任後も続けており、最近は庭に咲き始めたカラーやシャクヤクを飾っています。花を飾ることの理屈はうまく表現できませんが、花を見ると心が和みます。学校の雰囲気づくりに少しでも役に立てれば幸いです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月27日(火)
授業 美術Ⅰから
「校長のつぶやき」5月27日(火)
5月25日(月)2・3時間目 美術Ⅰ(岩佐先生)の授業を参観しました。「絵の具を知ろう」という課題で、いろいろな絵の具とその特徴について学ぶ内容でした。
油絵の具、水彩絵の具、日本画の絵の具、アクリル絵の具の現物が用意されており、実際に着色した際の様子も直に観察することができました。日本画の絵の具のザラザラとした質感などは、私自身も初めての体験でした。また、油絵の具より前には「テンペラ画」が主流で、卵の卵黄を原料としていることや、かの有名なレオナルドダビンチ作「最後の晩餐」もその技法で描かれていることを学びました。
授業の後に、「モナリザ」はポプラの木の板に油彩で描かれているので顔料が剝がれやすく、もう2度とフランスから出せることが難しい(過去に2回ほど海外で展覧会があり、そのうちの1回が日本)と言われていることなども教えてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月26日(月)
可能性は口から始まる
「校長のつぶやき」5月26日(月)
5月23日(金)の1時間目 3学年合同のホームルームを参観しました。内容は、一般社団法人ハッシャダイソーシャルから派遣された講師の講話でした。派遣元のハッシャダイソーシャルは、高校や児童養護施設、少年院等を対象に講演活動に取り組んでいる団体です。昨年度もオンラインでの講話に協力してもらい、今年度は講師に直接来校してもらうことになりました。講師の大本観月(おおもと みずき)さんは、通信制高校を卒業後に、自動車関係の会社に就職し、その後ミュージカル俳優を経て現在に至っているとのことです。講話の中で、教訓となることばをいくつか示してくれました。タイトルの「可能性は口から始まる」はその中の1つで、やりたいことを自分の中にしまっておくだけでなく、言葉にすることによって、誰かが気がついてくれて動き出すことがあるとのこと。その他にも、大本さんの実体験から生まれた言葉をいくつも示してくれました。私自身、志の高い人間の話を聞き、刺激を受けた貴重な時間となりました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月23日(金)
電話でもLINEでも
「校長のつぶやき」5月23日(金)
昨日は、広島県福山市の通信制高校の事件を受けて、生徒たちへ緊急メッセージを発出しました。悩みがあったら一人で抱え込まないことを知ってもらうためです。私はこの3月まで茨城県教育委員会の生徒指導担当部署で働いていました。相談機関の運営や周知も仕事の1つでしたが、茨城県では30数年前から運営されている子ども(18歳までが対象)専用の電話相談機関「子どもホットライン」や、6年前から始まったLINEやWEBでの相談「いばらき子どもSNS相談」などがあります。他にも様々な行政機関や各種団体が相談窓口を開設しており、社会全体で子どもたちの悩みを受け止める体制が整っています。生徒の皆さん、苦しくても絶対に一人で悩まず、誰かに相談してください。
校長 皆藤正造
-
2025年5月22日(木)
特別活動・ひたち海浜公園BBQ
「校長のつぶやき」5月22日(木)
昨日、ひたち海浜公園にて特別活動の行事として、バーベキューを行いました。目的は新入生及び在校生のふれあいの場を作り、新しい友人をつくることとしています。生徒57名(1年生25名 2年生22名 3年生 10名)と職員が9名参加し、9つのグーループに分かれて実施しました。火起こしから始まり、鉄板を用意し、肉や野菜の食材を準備し、火が通った食材から食事をはじめ、最後のメニューは焼きそば、デザートには焼きマシュマロもあり、生徒たちにとって楽しい時間となったようです。
先日、来校した卒業生に水戸平成学園高等学校の良さを聞いたところ、「毎日スクーリングがあるし、特別活動が充実しています。」と答えてくれました。私にとって、卒業生の言葉を実感できた一日でした。
校長 皆藤正造
-
2025年5月22日(木)
学校からの緊急メッセージ
学校からの緊急メッセージ
昨日、広島県福山市の通信制高校にて、生徒が同じ学校の生徒3人をナイフで切りつけるという痛ましい事件が発生しました。事件の詳しいことはわかりませんが、事件を起こした生徒は、何かしら悩みを持っていたことかと思います。
皆さんも、いろいろな悩みがあると思いますが、苦しい時は一人で悩みを抱えることなく、誰かに相談してください。
相談する相手は、家族、学校の先生、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、自分の悩みを打ち明けられる相手なら誰でもいいです。また、電話相談やラインでの相談など、様々な相談機関もたくさんあります。
悩みは、人に話すことで小さくなります。生徒の皆さんは、悩みを1人で抱え込まないようにしてください。
令和7年5月22日
水戸平成学園高等学校 校長 皆藤正造
-
2025年5月21日(水)
授業 地理総合から
校長のつぶやき」5月21日(水) 授業 地理総合から
5月20日(火)2時間目 地理総合(矢野先生)の授業を参観しました。地理総合は必修科目であり、教科の内容は地理の一般常識が多く、就職試験等で問われることが多いそうです。
プリントの冒頭で生徒たちに課していた課題が、私自身も学び直しできたところでもありましたので、掲載いたします。
1 日本の人口(令和5年4月) 約1億2千500万人
2 日本を囲む4つの海の名称 太平洋 日本海 オホーツク海 東シナ海
3 世界の3つの大洋は 太平洋 大西洋 インド洋
4 世界の標準時は、どこの国を基準としたか イギリス
5 日本の標準時子午線はどこにあるか 兵庫県明石市 東経135°
授業終了後、私は職員室で矢野先生にいろいろ質問し、学ばせてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月21日(水)
授業 地理総合から
「校長のつぶやき」5月21日(水)
5月20日(火)2時間目 地理総合(矢野先生)の授業を参観しました。地理総合は必修科目であり、教科の内容は地理の一般常識が多く、就職試験等で問われることが多いそうです。
プリントの冒頭で生徒たちに課していた課題が、私自身も学び直しできたところでもありましたので、掲載いたします。
1 日本の人口(令和5年4月) 約1億2千500万人
2 日本を囲む4つの海の名称 太平洋 日本海 オホーツク海 東シナ海
3 世界の3つの大洋は 太平洋 大西洋 インド洋
4 世界の標準時は、どこの国を基準としたか イギリス
5 日本の標準時子午線はどこにあるか 兵庫県明石市 東経135°
授業終了後、私は職員室で矢野先生にいろいろ質問し、学ばせてもらいました。
校長 皆藤正造
-
2025年5月20日(火)
職員会議から
「校長のつぶやき」5月20日(火)
5月19日(月)の午後4時15分から、職員会議がありました。毎月1度行われる会議で、翌月の行事等の確認をしています。
私からは、ある教育雑誌に掲載されていた「面倒見がよい大学」のランキングを紹介し、本校との共通点があるかどうか確認しました。
1位 金沢工業大学(私立 石川県) 20年連続1位 「学生を最大限に成長させることを組織的に行っている」「個々の学生に適した学習プログラムの提供」
2位 東北大学(国立 宮城県)「教員と学生の距離が近く、丁寧な指導が行われている。」
3位 武蔵大学(私立 東京)「1年次からゼミが必須、徹底した少人数教育」
4位 国際教養大学(公立 秋田県)「すべてが英語の少人数授業」「1年間の留学事務」
5位 福岡工業大学(私立 福岡県)「経営スローガンに For all the students」
上記の特徴を参考にしながら、生徒一人ひとりを多面的に理解し、丁寧な支援を通して生徒が成長できる学校を作ります。校長
皆藤正造
-
2025年5月19日(月)
熱心な先生たち
「校長のつぶやき」5月19日(月)
5月15日(木)の午後に、茨城県通信制高等学校等連絡協議会がオンラインで開催され、その中で午後3時からは第1回教員研修会がありました。本校からは、皆藤、茂垣教頭 郡司 植松が参加しました。今回の研修講師は、NHK学園高校の先生方4名で、テーマは「通信制高校における主体的・対話的な学び 協働的な学びの取り組み」でした。主な内容は、地学と地理 英語と音楽のコラボ授業 オンラインでの特別活動等の実践発表でした。発表後に質疑応答の時間になりましたが、真っ先に質問したのが茂垣教頭で、その後も各学校の先生方が次々と質問し、協議が約20分続きました。教育関係の研修会には数多く参加してきましたが、質問や意見が次々と出されて活発な協議となる研修会は稀です。県内の通信制高校は熱心な先生方が多いです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月15日(木)
自己を見つめよう
「校長のつぶやき」
私の学校での日課は、各教室で行われている授業を参観することです。内容によっては、私自身の学びにつながることも多くあり、一生徒になったつもりで、先生たちの言葉に耳を傾けます。
今日の1時間目、茂垣教頭先生による「家庭基礎 家庭総合」の授業の中で、「自己概念を高める」ことについて指導していました。自己概念とは自分について持っているイメージのことで、うまくいかない時でも自分は価値のある存在だと忘れないことが大切だそうです。教科書に「自分を見つめよう」として、3つの問いがありました。
1 自分の好きなところやプラス面を挙げよう。
2 今までに周囲の人(家族や友達、先生など)から褒められたことや感謝されたことを挙げよう。
3 自分が貢献していることについて考えよう。
皆さんも、この問いについて考えてみませんか。
校長 皆藤正造
-
2025年5月14日(水)
視野を広げる
「校長のつぶやき」5月14日(水)
本校は毎年、茨城キリスト教大学で心理学を学ぶ大学院生を心理実習生として迎えています。2年間の実習で、1年目は主に保健室での実習、2年目は個別の相談実習等も行います。
今日は、本年度から派遣される大学院生3名の初めての実習日なので、最初に私から実習の心構え等について話をしました。その際、心理学を大学で4年間学んできた学生さんたちなので、私から「レジリエンスを高めるために大切なこと」として質問を出し、回答を求めました。レジリエンスとはここ最近注目されてきた概念で、いわゆる「立ち直る力」「心のしなやかさ」のことを指します。どうすればレジリエンスを高めることができるか、ここ数年はいつも考えています。1人の実習生の回答は「視野を広げることかと思います。その時はつらいと感じたことも、時が経ってみると案外大丈夫なことがあるからです。」でした。私にとっては至極納得できる言葉でした。
校長 皆藤正造
-
2025年5月13日(火)
体育集中講義から
「校長のつぶやき」5月13日(火)
今日は体育集中講義があり、午前中がボウリング、 午後は千波湖ランニングを実施ました。午前中のボウリングは、水戸グリーンボウルを会場に46名が参加しました。平日の午前中でもあり、シニアの愛好会と思われる方たちが数組楽しんでおりました。本校から参加した生徒たちは、13のグループに分かれ和気あいあいとボウリングを楽しみました。
午後の千波湖ランニングは22名が参加しました。千波湖のランニングコース(1周3km)を2周するのが授業のノルマです。今日は気温が高く、熱中症が心配されましたが、幸い心地よい風がふいてくれたおかげで、全員が無事に完走・完歩することができました。
ある健康雑誌に、45分以上運動すると幸せホルモンが出ると記載があったので、私自身、意識的に体を動かすようにしています。今日は生徒たちの活動を直接見ながらたくさん運動できた一日でした。
校長 皆藤 正造
-
2025年5月13日(火)
環境は人をつくる
「校長のつぶやき」5月12日(月)
水戸平成学園に赴任して約1か月半が経ちました。毎朝職員は、出勤後に校舎内の分担(月ごとに変ります)を、掃き掃除やモップ掛けなどをしてから自分の仕事に取り掛かります。私も雑巾を絞って、職員室や近くの部屋のテーブルを拭いています。きれいな環境で生徒を迎えるための水戸平成学園高校の伝統です。教室の机やいすにも落書き等はまったくありません。生徒用の机の天板にいたってはピカピカの状態なので職員に聞くと、年度の終わりに必要に応じてニスを塗っているそうです。創立20年になりますが、大切にされてきた校舎をはじめきれいな環境で人を育てる学校です。
校長 皆藤正造
-
2025年5月10日(土)
自分を高める
「校長のつぶやき」5月10日(土)
今日は3学年対象の進路別合同説明会があり、午前中は大学進学希望の生徒と保護者、午後は専門学校希望の生徒と保護者が来校しました。進路指導担当の出沼教諭が、今後の見通しや確認事項等を説明しました。私は冒頭にあいさつさせていただきましたが、その際に生徒に伝えたことばが「自分を高める」です。
これからの将来は予測不能の社会になると言われています。いわゆる「いい学校を出て、いい会社に就職すれば安泰」ではなくなることは明らかです。ですから、これからの社会を担う人たちには、求められることが多々あるようです。大切なことは、いつも自分を高める気持ちを持って努力を重ねることではないでしょうか。この学校を巣立つ生徒たちには、様々な場面で私の思いを伝えていくつもりです。
校長 皆藤正造
-
2025年5月9日(金)
誰といたか
「校長のつぶやき」5月8日
今日の5校時終了後、植松先生が指導する探究ゼミに参加した2年生16名が企画した、新入生対象のウエルカムパーティーが行われました。参加した2年生は、4月25日に事前打ち合わせを行い、3つのグループに分かれてレクリエーションを企画して今日を迎えました。1年生からは31名(本人の希望による)が参加し、2年生のリードで、新しい仲間と楽しい時間を過ごせたようです。
そもそも学校とは、同じくらいの年齢の子どもたちが一緒に時間を過ごす場所です。「何をしたか」よりも「誰といたか」を強く心に刻む場所なのかもしれません。水戸平成学園での出会いが新しい自分をつくるきっかけになることを願っています。「 校長 皆藤正造
-
2025年5月8日(木)
教育は人なり
「校長のつぶやき」5月8日
今日はスクーリング開始2日目です。生徒たちが2階の多目的ルームで談笑する光景を見ていると心が和みます。4月の学年ガイダンスで生徒たちに伝えましたが、高校時代は人生の中で最も自由を謳歌できる貴重な時です。平成学園の生徒たちが笑顔で毎日生活してほしいと願っています。
さて、本校の評判に関する2つ目の理由は、教師集団の力量の高さです。4月に赴任してから、教職員の働きぶりを見ていると気が付くことがあります。相手が保護者であっても生徒であっても、柔らかい言葉で丁寧に対応してくれています。本校には途中からの転入学相談が入ることが少なくありません。そのような場面では、どの教職員も親身の対応を心がけています。彼らはいつもと同じ対応をしているつもりだと思いますが、3月まで外にいた私の眼にはその丁寧ぶりは際立っています。平成学園の強みは、引き出しが多く心が広い教職員です。
校長 皆藤正造 -
2025年5月7日(水)
壁のない職員室
「校長のつぶやき」
このコーナーを利用して、学校生活を通して私が感じたことや在校生や保護者の皆様にお伝えたいことを掲載させていただきます。
4月に着任する以前から、水戸平成学園高校は「生徒への面倒見がいい学校」としての評判を耳にしていたので、そのワケを知ることを私自身へのミッションとしました。その1つとして「壁のない職員室」を挙げます。校舎に入って1階の中ほどに「職員室」があります。一般的な学校のように壁で仕切られているわけではなく、カウンターのような構造になっており、生徒たちは廊下から直接教員に声をかけることができますし、教員たちも登校してきた生徒へすぐ声をかけられます。この設計については、中村三喜前校長(現特別顧問)が携わったとのことです。本校の目指す学校像の1つ「教師と生徒のface to face」の実践に繋がっていることは間違いありません。
校長 皆藤正造 -
2025年1月22日(水)
「茨城いのちの電話」への寄付金
本校生徒の皆さんは、学校の自販機で飲み物を買ったことはありますか?
実は、売り上げの一部が社会福祉事業のための寄付金にあてられています。
この度、2024年の寄付金「36,660円」に対するお礼が「社会福祉法人 茨城いのちの電話」より届きましたので報告いたします。
次に自販機で飲み物を買う際には、自分の行動が誰かのためになっていることを思い出してもらえると嬉しく思います!
リンク:茨城いのちの電話HP -
2025年1月21日(火)
茨城新聞文化福祉事業団による「愛の募金」~12/29 茨城新聞~
茨城新聞文化福祉事業団による「愛の募金」についての記事が茨城新聞に掲載されました。寄付の際には、文化祭実行委員長の小沼翔太さん(2学年)が代表として茨城新聞社を訪問しました。

-
2024年8月14日(水)
8.14(水)原風景
2024年8月14日(水)
生徒の皆さんへ
「原風景」
私は1944年の生まれですので、今月19日を迎えると満80歳になります。そして、それはお盆の時季でもあるので、久しぶりに昔よく通った道や遊んだ場所を歩いてみると、幼い頃の記憶がよみがえり、懐かしさや、すっかり変わってしまった風景への哀惜、もう二度とあの頃には戻れないのだという寂しさなど、さまざまな思いがこみ上げてくる。
同時に、家族や友だち、その時身近にいてくれた人たちの姿や言葉が思い出されて、それらが自分の物の見方や考え方の原点になり、今日まで折々に支えとなってきたことに改めて気づかされる。
変わりゆく時代の中で、人は時に過去をたどり、いつまでも変わらない自らの原風景に立つ。そうすることで自分を確かめ、明日に希望をつないで、新たな人生を紡いでゆけるのだろう。
そして、自分の生きた証もまた決して消えることなく、必ず誰かの心の風景に刻まれてゆくはずである。できることなら、その人が苦しいとき、迷ったときに立ち返る拠り所となって、勇気を与えられるような、そんな生き方をしてゆきたい。
周囲の大切な人たちの心に、自分はどんな風景を残すことができるのだろうか。校長 中村三喜
-
2024年4月9日(火)
校長より生徒の皆さんへ【第18回】
校長より生徒の皆さんに第18回目の言葉です。
2024年4月9日(火)
生徒の皆さんへ
「新しい夢」
今の小学生に将来の夢として、なりたい職業を尋ねると、男の子ならプロスポーツ選手やゲームクリエーター、女の子なら保育士、医師、パティシエといった答えが返ってくるという。時代の違いはあるけれど、子供達の夢はいたって明快、語らう姿を想像するだけでも微笑(ほほえ)ましい。
ところが夢のとおり叶うかはさておき、大人になって職に就き、幾春秋が過ぎるうちに、いつしか新しい夢を持たなくなってしまう。
いやいや仕事には常に目標があり、目標を達成すればまた次の目標が与えられ、倦(う)むことはない。そう言い切れるならばそれはそれで結構なことだ。
とはいえ、目標は一つの目安にすぎない。まして目標達成のために汲々(きゅうきゅう)とし、真の仕事の喜びや自分を高める楽しさを見失ってはつまらない。
仕事に限らず、いつも夢を持ち続けよう。日常の些事(さじ)に追われて疲れを覚えても、夢を思い起こせば元気が戻ってくる。
人生は夢あればこそ輝くことを忘れないでいたい。
校長 中村三喜